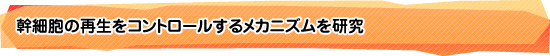フクロウ博士の森の教室 シリーズ1 生命科学の基本と再生医療
第1回 いくつに切られても再生するプラナリアの不思議
プラナリアから再生医療が学ぶものはたくさんある
京都大学大学院 阿形清和教授 インタビュー

Profile
阿形 清和(あがた・きよかず) 1954年生まれ。大阪生まれ、東京育ち。1983年京都大学大学院理学研究科・生物物理学教室・岡田節人研究室卒業。1983年基礎生物学研究所助手、1991年より姫路工業大学(現兵庫県立大学)理学部生命学科助教授。このころからプラナリアの研究に着手。2000年より岡山大学・理学部 教授。2002年より理化学研究所発生再生科学総合研究センター・グループディレクター。2005年より京都大学大学院理学研究科・生物物理学教室教授。
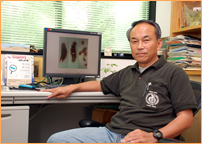
───プラナリアの研究でおもしろいのはどんなところですか。
実際に野外に出てプラナリアを小川や池で捕まえるところから楽しいですよ。プラナリアは、日本中どこにでもいる生き物なので、ぜひ捕まえて飼育にチャレンジしてほしいですね。 肉眼で見ると、ヒルと見分けがつきにくいけれど、学生たちが顕微鏡でのぞいたときに発する言葉は「きゃ、かわいい!」です(笑)。目に愛嬌があるんです。
───もっと原始的な動物なのかと思っていましたが、お話をうかがうと、なかなか賢いですね。
光や匂いなど、各種の情報を統合する脳の基本的機能がちゃんと備わっています。プラナリアを研究していて、もっとも感嘆するのはやはりいくつに切っても再生する、再生能力の高さですが、プラナリアにしてみると、別に切られるために再生能力を持っているわけではなくて、環境に応じて個体を増やすためなんです。ある程度大きくなると、咽頭の少し下がくびれて2つに分かれ、それぞれが個体になります。ところが栄養状態が悪くなると、ひとつの個体の中に精子と卵子をつくり、有性生殖をする。とても戦略的な生き物なんですよ。
───「フクロウ博士の森の教室」では、プラナリアの再生能力が高いのは、全能性の幹細胞(万能細胞)を数多く持っているからだと教えていただきました。
幹細胞というのは、いろいろな種類になれる細胞でありながら、自分自身は未分化のまま自分を増やして(自己増殖して)、必要に応じて神経細胞や筋肉細胞といった分化した細胞を供給するという、たいへん柔軟性に富んだ細胞です。プラナリアの全身の細胞の10〜20%が幹細胞なんです。