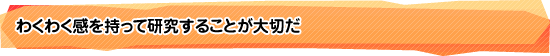───先生はなぜプラナリア研究など、生命科学の研究者になろうと思ったのですか。
高校時代、生物学者として有名な京都大学の岡田節人(おかだ・ときんど)先生の「細胞の社会」という本を読んで感動し、高校生なのに新幹線に乗って京大の授業を大学生のような顔をして受けていました。京大に合格して、岡田先生に「イモリの再生を研究したい」といったところ、「おもろいやっちゃ」とかわいがってくれました。
ただ、イモリの研究ではとても岡田先生には勝てない。それなら、プラナリアの研究で楽しもうと考えたのです。
───そのときプラナリアの研究をして、成功するという見通しをもっていたのですか。
いいえ、その先になにがあるのか、まったく見えていなかった。
ただ、プラナリアの再生にどのような遺伝子がどのようにかかわっているかがわかってきたときは、無茶苦茶楽しかったですよ。そういうときは研究に勢いがあり、わくわく感があった。サイエンスが上り坂にあるときがおもしろくて、わくわくしながら研究することが大事なのです。
───中・高校生に向けてメッセージをいただけますか。
これから研究者の世界は、ますますグローバル化が進むと思います。これに対応するには、中・高校時代から英語をマスターすることが欠かせません。それと、研究者になるにしろ、医療関係に進むにしろ、プロ意識を持つことが大切です。サッカーでも、日本はJリーグが発足するまでは世界で勝てなかった。研究者もプロ意識を持ってはじめて世界で通用するのです。
それと、何にでも興味を持つこと。動物について研究しているから植物に興味がないというのではだめ。何事も経験することによって、新しい発見につながるからです。
(2009年6月2日取材)
参考図書

『切っても切ってもプラナリア』
阿形清和/文 土橋とし子/絵
岩波書店刊 定価1800円+税
2009年6月の新装・発刊された阿形先生の本。プラナリアの捕まえ方、切り方、再生のしくみなどが詳しく書かれている。