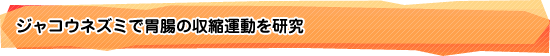───モチリンを研究する時には、どんな方法で行うのですか。その一端を教えてください。
こういった身体の働きを調べる研究では、まず、ラットやマウスなどの小動物を使って、その研究結果を踏まえてヒトに応用していくのが一般的です。ところが、不思議なことにラットやマウスにはモチリンがないんです。したがって、モチリンの研究には、他の動物を使わなければなりません。サルやイヌはモチリンによく反応するのですが、扱いにくいという欠点があります。
───それはたいへんですね。どんな動物を使っているのですか。
ウサギもモチリンを持っているけれど、草食動物だから消化管の働きがヒトとは違ってこれも適しません。そこで、モチリンを持っていて、ラットやマウスの代わりに利用できる小型実験動物を探して、たどり着いたのがジャコウネズミです。ネズミという名前がついているけれど、モグラの仲間です。「ネズミ」と名のついた「モグラ」となるとややこしいので、研究者の間では通常はスンクスと言っています。スンクスは日本で実験動物化された唯一の小型動物なんですよ。
なによりありがたいのは、胃の構造がヒトに似ていること。ラットやマウスの胃は一部粘膜が無いのですが、スンクスの胃は、ヒトと同様に胃全体が粘膜に覆われているんですね。
───スンクスの消化管で収縮運動を研究されたわけですね。
そうです。研究してみると、スンクスでも空腹になると胃と十二指腸の消化管の収縮が定期的に起きていることがわかりました。その収縮の間隔はヒトやイヌの場合、90~120分おきですが、スンクスでも80~140分でそんなに変わりません。この研究から、どうも動物には、空腹時の消化管の収縮間隔を決めいている基本的なメカニズムがあるのではないかと考え、いま研究を進めています。
スンクスは、夜行性の動物なので、夜に活動して、食物を摂取します。一方、昼は眠っていて、ものを食べません。スンクスの消化管の収縮運動を見ると、空腹時に見られる強い収縮が昼に起きています。ヒトは昼行性ですから、スンクスとは逆に、夜間、モチリンが働いて消化管がたくさん収縮しています。この消化管の収縮が胃や腸の中の食べ物のカスなどを掃除して、朝には、ものを食べたくなるようにしているんだといわれています。
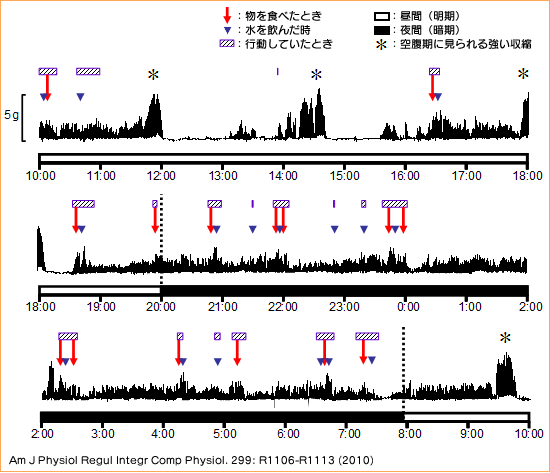
▲ スンクスの消化管の収縮状況