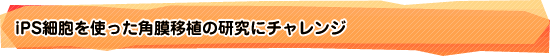───手術が終わって、視力が改善するまでには時間がかかるのですか。一度改善されるとずっと改善したままの視力を保てるのですか。
成功した場合には、手術の後はすぐに視力は改善しますよ。何年かして視力が落ちてくる場合と、ほとんど落ちないケースとがあります。なぜそういうことが起きるかというと、口の中の粘膜の幹細胞を培養して使った場合、ほんものの角膜上皮幹細胞を使っているわけではないので、移植した後に角膜上皮細胞層の代替には完全にはなれないケースが出てくるのではないかと思っています。
───これからの研究テーマについて教えてください。
角膜のうち、上皮層と実質層、内皮層では、幹細胞の質も違うので、実質、内皮への移植は、口腔粘膜から培養した幹細胞は利用できません。いま、ヒト用の内皮細胞シートをつくり出すことに実験では成功しているので、この研究を進めたいと考えています。
それと、再生医療を広めていく技術やマシーンの開発に力を注ぎたいと思っています。いま角膜上皮シートをつくるためには、無菌状態のクリーンルームで行う必要があり、この部屋を維持するだけで年間数千万円もかかってしまう。これではコストの面からも普及していきません。
そこで、企業と共同で“自動培養機器”の開発を手がけています。これができると、角膜上皮細胞だけでなくいろいろな部位の再生医療に利用する組織を自動で培養することができ、再生医療の普及につながると思っているのです。

▲ クリーンルームでの培養作業風景
───iPS細胞を使った角膜再生にもチャレンジされていますね。
今後、私たちの最重要な研究テーマになっているのがiPS細胞を利用した角膜再生です。さきほど、お話ししたように、角膜上皮の再生に使っているのは口腔粘膜の幹細胞ですから、ほんものの角膜上皮にはならない。やはりどんな細胞にも分化することのできるiPS細胞から、ほんものの角膜上皮細胞をつくって移植することが理想なわけです。iPS細胞を使えば、角膜内皮細胞もつくれるわけですから、魅力がある研究ですね。
いま、iPS細胞から角膜の細胞に分化誘導する技術はできてきているので、iPS細胞から分化させた細胞を再生医療に使っても、腫瘍化しないなどの問題をクリアできれば、可能性があると思います。