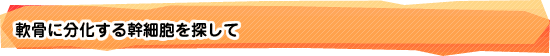フクロウ博士の森の教室 シリーズ1 生命科学の基本と再生医療
第15回 膝軟骨と半月板の再生
研究の成果を臨床に活かし、患者さんに感謝されるのが仕事のやりがい
東京医科歯科大学 軟骨再生学 関矢一郎教授 インタビュー

Profile
関矢 一郎(せきや・いちろう)
1990年東京医科歯科大学医学部卒業。90年同大学整形外科医員。以後、九段坂病院整形外科、川口工業総合病院整形外科、東京医科歯科大学整形外科医員などを経て、96年東京医科歯科大学大学院へ。2000年MCPハーネマン大学遺伝子治療センター(米国 フィラデルフィア)ポスドク、トゥレイン大学遺伝子治療センター(米国 ニュー・オーリンズ)ポスドクの後、2002年東京医科歯科大学大学院運動器外科学助手。2006年同大学院軟骨再生学准教授。2011年より現職。
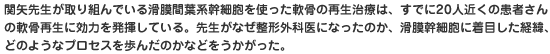
───現在の研究を始められたきっかけ、背景をお話しください。
1990年に医学部を卒業し、6年間の臨床トレーニングを経験してから大学院に入りました。
大学院では分子生物学の手法を用いた研究を行いましたが、この頃、軟骨の細胞分化において中心的な役割を担うSox9という転写因子の機能がわかりはじめてきました。この転写因子はいろいろな細胞を軟骨に分化させることができるもので非常に注目されました。
さらに、1999年に有名な科学雑誌「サイエンス」に骨髄由来の間葉系幹細胞に関する報告が大きく掲載されたんです。それで私は、これからは骨髄由来の間葉系幹細胞を使った再生治療の時代になると考え、その分野の研究をしたいと考えるようになりました。
そこで2000年に骨髄の間葉系幹細胞の研究が盛んな米国の大学に留学しました。ただ、ここでは神経系の研究がメインだったので、軟骨を専門にするのは私が初めてでした。
───その間葉系幹細胞ってどんなものですか。わかりやすく教えてください。
私たちの身体は、受精卵から細胞分裂して、初期の頃に外胚葉、中胚葉、内胚葉の3つに分かれます。外胚葉からは脳や脊髄など神経組織、皮膚などが、中胚葉からは骨、軟骨、脂肪、筋肉、血管などが、内胚葉からは肝臓、胚、胃などの臓器が形づくられていって、人体ができあがるわけですね。
間葉系幹細胞というのは、主に中胚葉を起源とし、骨芽細胞、脂肪細胞、筋細胞、軟骨細胞などへ分化する能力をもつ細胞です。こうした性質をもっているため、骨や血管、心筋の再構築などの再生医療への応用が期待されているのです。さらに、神経細胞や肝細胞に分化するとも考えられています。
───すると、その間葉系幹細胞から実際に軟骨がつくられるという研究成果がその後すぐ登場したのですか。
いや、「サイエンス」に論文は出たものの、実際に間葉系幹細胞から軟骨に分化させるのは容易ではなく、書いてあるとおりに行ってもなかなか軟骨をつくることはできませんでした。そこで留学中は、骨髄幹細胞をより効率よく体外で軟骨に分化させる方法を検討しました。
───先生が本格的に軟骨への分化の研究を始めたのはいつからですか。
留学から帰って、東京医科歯科大学の運動器外科学助手として、2002年頃から骨髄由来の間葉系幹細胞を用いた軟骨の再生医療の開発に本格的に取り組みはじめました。ただ、骨髄からは間葉系幹細胞の数をすべての患者さんから安定して確保するのが難しかったので、いちばん軟骨に分化しやすく、数の確保が容易なのはどの間葉系幹細胞なのかを研究していきました。幸い、膝の手術に携わっていたため研究に利用できる膝周りの組織がたくさん手に入りました。それで実験をしていったところ、滑膜由来の間葉系幹細胞がいちばん軟骨になりやすく、安定して多くの細胞を獲得できることがわかり、骨髄から滑膜由来の研究へとターゲットを変えていったわけです。