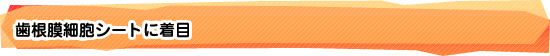フクロウ博士の森の教室 シリーズ1 生命科学の基本と再生医療
第17回
歯ナシを防ぐ話
〜歯周組織の再生
歯根膜細胞シートを使って
歯周組織の再生医療に挑む
東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 特任講師
岩田隆紀教授 インタビュー

Profile
岩田 隆紀(いわた・たかのり)
2002年東京医科歯科大学大学院修了。歯周病科に在籍し、研究と臨床に携わる。2004年米国ミシガン大学に留学。2007年東京女子医科大学先端生命医科学研究所に移る。東京女子医科大学特任助教を経て、2010年より同大学特任講師。大学院時代より歯根膜に関わる研究に従事する。歯学博士。2012年度The Johnson & Johnson Innovation Award受賞。
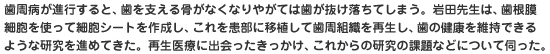
───先生が歯科医をめざしたのはなぜですか。
実家が歯医者なのでゆくゆくは開業しようと考えていました。歯周病科を選んだのは、患者数が多いことと、歯周組織が健康でないとどんなに良い詰め物をしても歯が抜け落ちてしまうなど、歯の健康を考える上ではとても重要だと考えたからです。
───細胞を使った再生医療に携わるようになったのはどんな経緯からですか。
アメリカ留学から帰国し東京医科歯科大学で医局員として臨床に従事していた2006年に、私の恩師の石川烈先生が、東京女子医科大学の先端生命医科学研究所に移られました。そして、「細胞シートを使った再生医療がおもしろい。君は細胞生物学も勉強してきたのだから、やってみないか」とお誘いを受けたのがきっかけでした。
前の大学の医局でも細胞培養をやっていたのですが、最初は殖える細胞もあれば殖えない細胞もあったり、増殖にばらつきがあって、これで本当に細胞を使った再生医療なんてできるのかと思ったりもしました。臨床が忙しくてなかなか研究に打ち込めないジレンマもありました。
そこで、2007年に東京女子医科大学のこの研究所に移ってきて最初にめざしたのは、ヒトの歯根膜から歯根膜組織を採取してどんな歯からも培養を成功させることでした。私は研究者であると同時に週に1回歯科口腔外科の臨床医も担当させていただいたので、治療現場で抜いた歯がたくさん手に入って、それを培養の実験に使うことができたのは非常にありがたかったですね。
培養実験を繰り返すうち、歯根膜細胞をばらつきなく増殖させることができるようになり、細胞を使った再生医療も可能ではないかと考えるようになりました。それから大型動物の歯根膜細胞の培養を始めました。
当時はiPS細胞や幹細胞を使った再生医療が脚光を浴び始めた時代で、前の医局では実用化にはまだ時間がかかると考えていましたが、先端生命医科学研究所に来てみると、いろいろな人が当たり前のように幹細胞を使った細胞培養をやっていて、それを目の当たりにすると、これは歯の再生に応用できると確信しました。
───細胞シートとの出会いはいつ頃だったのですか。
2002年~2003年ごろに当時東京医科歯科大学にいらした石川先生と東京女子医大の先端生命医科学研究所の岡野光夫先生とがコラボして細胞シートの研究をなさっていて、私の3つくらい下の大学院生がラットで実験しているのを見たことがありました。その当時は、「へえ、東京女子医大ではそんなことやっているんだ」という感じでしたね(笑)。
でもこちらの研究所に移ってくると細胞シートの研究が盛んで、実際、角膜の再生治療に細胞シートが使われていて、論文にもなっているし、患者さんの声なども聞くことができ、これはすごい技術だなと再認識したわけです。
───再生医療の中でも、歯根膜を使った細胞シートのほうに可能性を感じたのはどんな理由からでしたか?
既存の再生治療法の中に「GTR法」という方法があることを「森の教室」でもちょっと触れましたけれど、この方法は歯周病によって歯を支える歯槽骨を失った場合、その欠損部に、メンブレンというコラーゲンや高分子化合物でできた膜を置くことで歯周組織再生のスペースを確保し、歯根膜細胞が増えてくるのを待つという治療法でした。私はこの方法は原理としては優れていると感じたのですが、でも、これでは自然に歯根膜細胞が増えてくるのを待つしかない、いわば、受け身の治療法だと感じたのです。
それなら、歯根膜細胞を培養して細胞シートをつくり、それを治療したい歯根膜の部分に入れてやれば、目的の細胞をより早く再生できるはずです。細胞シートは細胞自身が分泌したタンパク質を足場にするので無害ですし、生体に近い組織ですからより早く組織形成が起こると考えました。