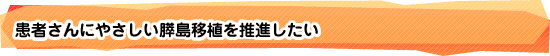フクロウ博士の森の教室 シリーズ1 生命科学の基本と再生医療
第19回 膵島移植による糖尿病の治療
ロマンを持って、それを達成する努力をしてほしい
福島県立医科大学 臓器再生外科学講座
後藤満一教授 インタビュー

Profile
後藤 満一(ごとう・みつかず)
1976年大阪大学医学部卒業。83年同大学医学部助手を経て、90年同大学助教授に。98年福島県立医科大学第一外科教授に就任。米国ハーバード大学、UCLA、ウィスコンシン大学、カナダ・アルバータ大学などで膵臓及び膵島移植の研究、研修に携わる。
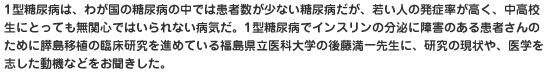
───糖尿病の中でも1型糖尿病の治療に力を注いでおられます。
2型糖尿病については、多くの人が知っていますが、1型糖尿病については、日本人の糖尿病患者のうち数%くらいしかいないということもあり、よく知らない人が多いようです。しかし、1型糖尿病は、膵島にあるインスリンを分泌するβ細胞が自己免疫による攻撃などを受けて壊れてしまい、血糖値が高くなってしまいます。食事や運動などによる生活習慣の改善では治療できず、毎日、インスリン注射をしないと生命にも関わることになる厄介な病気です。
しかも、1型糖尿病は、膵島から分泌され、血糖を上げる働きをするグルカゴンというホルモンも低血糖刺激では分泌増加がおこらないため、インスリンを打ち続けると血糖値が下がり続ける「低血糖症状」をおこしてしまうのです。インスリンを過剰投与したり、激しい運動によってブドウ糖を消費したりすると、血糖が極端に下がってしまい、急激にこん睡状態に陥ることもある。この人は気持ちよく眠っているのか、低血糖状態なのか、見た目には分からないのです。そうした低血糖状態が続くと脳の細胞に障害がおきることもあり、命の危険にもかかわる病気であるといえます。血糖値の変動が非常に激しくて、糖尿病の専門医でも血糖コントロールが難しいのです。
また、1型糖尿病は10代での発症が多く、14歳以下の小児の発症率は、1.5(/人口10万人)ですので、毎年1500人程度の方が発症していることになります。「森の教室」の読者の人にも全く関係のない病気とはいえませんね。
───インスリン注射でも血糖がコントロールできない場合に、膵臓移植や膵島移植を行うわけですね。
ええ、膵臓移植についていえば、糖尿病は合併症として糖尿病性腎症がでてきて、腎不全になる方がおられます。人工透析によって腎不全の治療をしているような患者さんなら、膵臓の移植だけでなく、腎臓の移植も同時に行う方が成功率は高いのです。一方、腎機能が保たれているが血糖のコントロールが糖尿病の専門医の先生の指導があっても大変難しい方がおられますが、その場合には膵臓単独移植を行うことがあります。膵腎同時移植や、膵単独移植は、全身麻酔をかけて、お腹を切り開いて行う開腹手術で、術後の合併症の問題も含めて、患者さんの負担も少なくありません。
一方、膵島移植は局所麻酔で、肝臓の門脈という血管に細い管を通して、膵島細胞の入った浮遊液を点滴で入れてやるだけで済みます。患者さんにとってはずいぶんやさしい移植法といえます。