───大学の進学振り分けではどの学科を選んだのですか?
高校生のときから基礎的な生物学に興味を持っていたので、理学部生物学科動物学を専攻しました。1クラス10人くらいで、担当の教授がとても厳しくて、授業を休むときにはちゃんと電話で連絡しなければならないし、5分でも授業に遅れるととても叱られました。
最も楽しかったのは生理実習です。神奈川県の三崎に臨海実験場があり、イカの巨大な神経の軸索を取ったり、シビレエイの電気器官の電位を測定したりしました。生き物の生存戦略に合わせて、いろいろな機能が発達しているのを見るのはおもしろかったですね。
───そのころから研究者になろうと思っていたのですか。
いいえ、研究者とか学者というのはみんなすごい人ばかりで、自分が研究者になれるとは思っていませんでした。ただ、実習で経験しただけでは学問としては不完全で、もっと自分でテーマを持って勉強したいという気持ちは持っていました。
そこで、とりあえず大学院の修士までは進んで神経機能の研究をやってみようと考えたのです。けれども東大にはその領域の研究室がなかったので、先生にお願いして東京都神経科学総合研究所に通うことにしました。そこでは骨格筋と運動神経を一緒に培養するとどんな変化が起きるのかを観察する研究をしました。とても興味深くて実験にのめり込んで、毎晩、終電まで研究し続けた思い出があります。
実験というのは誰もが知らない問題に挑んでいるわけで、正解に近づくにはどんな方法でアプローチすればいいか、それを自分で考えなければならない。謎解きのおもしろさを感じるとともに、今見ているものは世界中でまだ誰も見ていないものなのかもしれないという実験の醍醐味を味わうことができました。
そうこうするうちに、研究をしている以外の自分の姿を想像することができなくなって、ドクターコースに進もうと考えるようになりました。
───大学時代、エンジョイしたことはどんなことでしたか。

▲ 大学3年生頃 スキーサークルの仲間とともに(右から2人目)
大学に入ってからも音楽はずっと好きで、ヒットチャートをチェックしては、当時はCDを買うお金がなかったので、レンタルしてそれをテープに録音する作業をひたすらやっていました。Duran Duranやマドンナなどのアイドルも好きだったし、ポリス、トーキングヘッズ、ジェネシスなどもよく聴いていましたね。
それと大学生から大学院生のころは、比較的安く映画を楽しめる名画座や自主上映会でオードリー・ヘップバーンなどの古い映画を観たり、ビデオを借りてリュック・ベッソン、ティム・バートンなど好きな監督の映画をよく観ていました。
学部のころはスキーのサークルに入り、仲間が卒業して就職してからも一緒に滑りに出かけました。理系でも研究漬けどいうほどでもなかったのです。
───ドクターコースに進んでからはどんな研究をなさったのですか。
ホヤの卵を使った神経発生の研究に取り組んでいた高橋國太郎教授の研究室に入り、卵から様々な細胞が分化して脳が形成されていく過程で、どんなタンパク質情報や遺伝情報が働くのかを研究する岡本治正助教授のプロジェクトに参加しました。
私たちの持っている遺伝子の数は約2万個と言われていますが、生命の複雑な営みを説明するには、これだけの遺伝子だけではとても足りない。神経系では大脳、小脳、脊髄など、形も機能も違うものが一続きでできています。身体の神経系の軸にそって神経がどのように分化したのかを調べたところ、ある遺伝子にタンパク質の濃度の差(これを濃度勾配といいます)が関係して、形や機能が違ってくることがわかりました。たとえば、タンパク質の濃度の濃いところは脊髄に、低いところはもっと前の部分になったりするのです。つまり一つの遺伝子にさまざまなタンパク質の濃度情報が加わることで、形や機能を変えていくということです。
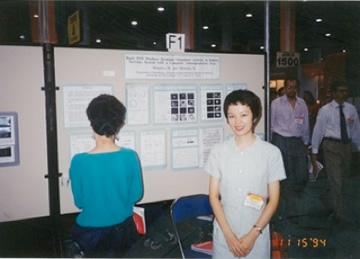
▲ 大学院時代、北米神経科学学会で。(ポスター発表)
───博士課程で取り組んだ神経発生の研究をさらに続けようと、本格的に研究者の道を志したわけですか。
そうですね。研究は好きだし、探究する喜びも感じていました。でも、職業としてやっていけるかどうかとなると、まだ自信がなかったというのが本当のところです。当時の日本の大学の環境は、女性が研究者としてやっていける状況は今ほど整っていなかった。女子の博士研究者など、うちの研究室では取らないという教授も多くいましたし、女性は研究者として能力が劣ると公言する人さえいたのです。
それならここまで頑張ったご褒美として、海外留学してみるのもいいかなと考え、ハーバード大学の発生学の教授の研究室でポスドクの研究員として留学することになりました。
その研究室は10人のスタッフのうち5人が女性でした。国籍もドイツ、イタリア、アメリカなどいろいろで、身近な友人としての女性研究者に初めて出会いました。彼女たちは、研究者といっても肩肘張るわけでなく、肩の力を抜いて自分のライフスタイルを持ちながら科学を職業にして楽しんでいる感じでした。私は彼女たちと出会って、女性だから研究者になってはいけないとか、研究だけに人生を捧げるとかではなく、自分らしいスタイルで研究する道があることを知りました。
留学中は、ドイツ人の女性研究者とメキシコやペルーに旅行して、途中でいろいろトラブルに遭ったり、それこそサバイバルツアーのような体験もして、おかげで世界観が広がったような気がします。

▲ ハーバード大学医学校遺伝学部門C.Tabin研究室のメンバーとともに。前列中央がテービン先生。

