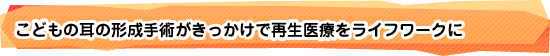フクロウ博士の森の教室 シリーズ1 生命科学の基本と再生医療
第28回 顔面の骨と軟骨の再生医療
10年計画でiPS細胞と3Dプリンターによる耳軟骨の再生にチャレンジ
東京大学大学院 医学系研究科外科学専攻
高戸毅教授 インタビュー

Profile
高戸 毅(たかと・つよし)
1979年東京大学医学部医学科卒業。同年、東京大学医学部附属病院形成外科研修医。
80年兵庫県立こども病院研修医。83年国立がんセンター頭頚科医員。85年都立墨東病院形成外科主事。87年静岡県立こども病院形成外科副医長。89年東京大学保健管理センター講師 90年文部省長期在外研究員としてトロントこども病院留学。92年東京大学口腔外科学講座助教授、96年同教授。97年東京大学大学院医学系研究科外科学専攻感覚・運動機能医学講座教授。2001年東京大学医学部附属病院ティッシュ・エンジニアリング部部長(兼任)
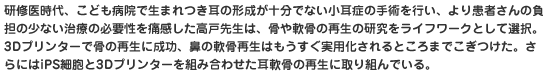
───高戸先生が再生医療を研究しようと考えたのはなぜですか。
私はもともとこどもが好きで、兵庫や静岡、トロントなどのこども病院で働いていました。その中には先天的な異常を抱えているこどもたちもいて、なんとか治してあげたいという気持ちが募りました。
再生医療をめざすきっかけになったのは、研修医として兵庫県立こども病院で研修医として勤務していた1980年ごろ、先天的に耳の形成が十分でない小耳症のこどもの手術をしたことでした。こどもの肋軟骨を3~4本採取して耳の再建手術をするのですが、患者さんの負担も大きく、何度も取ることはできないのです。
そうしたことから、軟骨をほんのちょっと採取して、そこからとった軟骨細胞を培養して耳の形に形成できないだろうかと、研修医の時から少しずつ実験などもしていました。
───当時はどんな実験をしていたのですか。
ラットを使った実験で、シリコンで耳の形をつくり、耳介をつくる細胞が含まれた軟骨膜をみじん切りにしてそのシリコンの耳にまいてみたのです。発想としては今でも間違ってはいなかったと思いますが、再生医療に必要な材料工学や細胞学の基礎的な知識がなかったし、臨床医、生物学、工学分野の知識を持ったスタッフによるチームづくりも行っていなかったので、ものにはならなかったですね。しかし、この時の経験が、再生医療をライフワークにしようと決意するきっかけになりました。
───再生医療の研究に本格的に取り組むための体制づくりの必要性をお感じになったわけですね。
ええ。国立がんセンターや静岡県立こども病院、東大医学部附属病院などで顔の形成外科を専門領域として診察や手術を行いながら、再生医療を実現するには、複数の研究分野のスタッフが集まり、企業との共同研究や治験ができる体制を整えていかなければならないと考えるようになりました。
そこで、2001年に東大病院にティッシュ・エンジニアリング部を設立しました。「ティッシュ・エンジニアリング」とは失われた身体の機能や組織を、生命科学と工学をうまく融合させてつくり出すことを目的とした研究領域で、アメリカではすでに研究が進んでいました。私は再生医療を本格的にやるためには日本でも導入する必要があると考え、部を設立するとともに部長職につきました。
───そこでは主にどんな研究を進めているのですか。
骨や軟骨、角膜、血管、腎臓などの再生をテーマとして研究を行っています。基礎医学から臨床、材料工学などの知見と技術を有機的に組み合わせながら、企業の協力も得て進めています。3Dプリンターによるカスタムメイド人工骨(CT-Bone)は、工学系研究科の鄭雄一教授など他分野の先生方との共同研究の成果です。
軟骨については自己修復ができないこともあり、再生医療への期待が大きいのですが、再生軟骨をつくるのはなかなか難しいのです。美容外科の隆鼻術として使っているのはゲル状の人工軟骨でしたが、これでは弾力が不足して医療用としては使うことができません。そこで、ティッシュ・エンジニアリング部の星和人特任准教授らと適度な硬さを持った再生軟骨をつくる研究をスタートさせました。
森の教室の本編でも話しましたが、2008年に耳から採取した軟骨細胞を患者さん本人の血清と細胞を増殖させるための増殖因子などを入れた液で培養して4週間で1000倍に増殖させる方法を開発しました。