フクロウ博士の森の教室 シリーズ1 生命科学の基本と再生医療
第30回
私たちの生命のプログラム
「エピジェネティクス」
健康と病気を理解する:エピジェネティクスの現在・過去・未来
熊本大学発生医学研究所 細胞医学分野
中尾光善教授 インタビュー

Profile
中尾 光善(なかお・みつよし)
1959年福岡県生まれ。1985年島根医科大学医学部医学科卒業。1991年久留米大学大学院医学研究科修了(医学博士、小児科医)。1992-94年ベイラー医科大学留学(米国) 研究員。1995-2001年熊本大学医学部 助手・講師。2002年より熊本大学発生医学研究所 教授。主な著書に『驚異のエピジェネティクス〜遺伝子がすべてではない!? 生命のプログラムの秘密』(羊土社)。「絵を描くことが好きで、いつかは画家になりたいと夢見ている」とのこと。
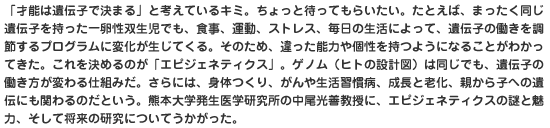
───エピジェネティクスとはどんな意味ですか。
20世紀の中ごろ、英国のコンラッド・ワディントンという学者が、生物の発生(身体つくり)について研究を行う中で、彼が初めて「エピジェネティクス」という言葉を用いたとされています。
「エピ(epi」とはギリシャ語で「~の上に」という接頭語で、「ジェネティクス」は「遺伝学」を意味します。つまり、「今までの遺伝学の上にあるもの」というほどの意味です。それまでは、いわゆるメンデルの法則にあるように、「遺伝」だけで生命現象を説明していたのですが、さらに「環境」を考える重要性を提示したのです。
具体的には、発生分化の過程で細胞の運命を決定するのは、遺伝因子と環境因子の相互作用であると考え、それを説明するために彼は「エピジェネティック・ランドスケープ」という一枚のスケッチ画を用いました。山の上の方に1個のボールがあり、このボールが山々の間の谷間を通って下の方に転がっていきます。その最終的に止まったところが、神経細胞であったり、血液細胞であったり、細胞の分化の終着点というわけです。そして、どのような経路でボールが転がっていくのかは、「遺伝と環境の相互作用」で決まるとワディントンは提唱しました。
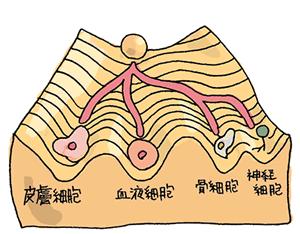
▲ エピジェネティック・ランドスケープ
───その後、エピジェネティクスの研究が進んでいったわけですね。
ええ。エピジェネティクスとは、ゲノム(設計図)の中から、使う遺伝子、使わない遺伝子を選ぶことによって、神経細胞、血液細胞、肝細胞など、身体を構成する質の異なった細胞をつくりだす仕組みであると次第に考えられるようになっていきました。
ヒトのゲノムには約2万5000個の遺伝子があります。このすべてに、<使う><使わない>という印がついています。そうして印づけられたゲノムのことを「エピゲノム」といいます。ゲノムの印づけは本編でも話したように、DNAのメチル化、ヒストンの修飾、そして、クロマチン(DNAとタンパク質が一緒になったもの)によって行われます。
こうしたゲノムの印づけは、細胞の分化や私たちの健康に重要な役割を果たすとともに、がんや生活習慣病などの発症に関わることが最近の研究で明らかになってきました。

