───大学院ではどんな研究を行っていたのですか。
大学院での研究は「ミツバチの社会性を支える神経基盤」というものでした。ミツバチはダンスをして仲間のハチに花のありかを知らせることで有名ですが、そうした社会性を持つためには記憶力がよいこと、ダンスをする意味を知っていることなど、高次の脳機能が不可欠です。そういった脳機能を支える遺伝子と神経細胞の関係などを探っていきました。この研究で学位を取ることができました。
───学位を取ってからはどうされたのですか。
学位を取ってから、これから何を研究しようか自分に問いかけながら、どんなアプローチによって研究を進めていくべきかを検討しました。「脳を理解する」といってもあまりに広範囲で漠然としています。そこで、音を聞いているときに、その意味を私たちがどのように理解しているのかを解明することを研究目標としました。
そのためには、神経細胞がどこにどのくらいあって、どうつながっているか、音がどのような神経回路で情報処理されているのかを調べなければなりませんが、ミツバチでは脳が大きすぎるので、もっと実験がしやすい動物を対象にする必要があります。そこで選んだのがショウジョウバエです。ショウジョウバエは個体同士の相互作用という複雑な本能行動を示す割には、脳が比較的小さく、分子遺伝学的なアプローチによる研究に適しているのです。
こうして、当時愛知県の基礎生物研究所にいらした伊藤啓先生(現・東京大学分子細胞生物学研究所准教授)の研究グループに参加して、ショウジョウバエが音をどのように理解しているかの研究を進めました。
───その後、ドイツに留学をなさっていますね。
はい。ショウジョウバエの聴覚システムについてアメリカの学会でポスター発表したときに、偶然隣同士になったドイツの研究者のMartin C. Göpfert が、ショウジョウバエの神経回路や聴覚システムの研究を一緒にやらないかと誘ってくれたのです。研究をさらに深めていきたいと考えていましたので、ドイツのケルン大学に留学しました。
───留学生活はいかがでしたか。
ドイツ語ができなかったのですが、フンボルト財団の支援を受けて2カ月間ドイツ語の特訓をして、なんとか基本的な会話くらいはできるようになりました。でも、十分に話せたわけではなく、切符を買うことさえままならず、最初はとても情けなかったですね。それでも、友人や同僚、通りがかりの人まで、たくさんの人が困っている私を見て手を貸してくれました。当たり前のことですが、人は支え合って生きていることを実感しました。 一方で、言葉が十分できなくても自分の意思を何とか伝えるという経験を何度もして、度胸がついた部分もありました(笑)。
───毎日の生活で苦労されたことは?
ケルンは大都市なので、和食屋は何軒かありましたが、ときどき無性にラーメンが食べたくなりましたね(笑)。いまはラーメンを食べたいとは思わないけれど、食べられない環境にいると、無性に食べたくなるものなのかもしれません。
それと、日本の本がなかなか手に入らないこともちょっとつらかったですね。ケルン大学にいる日本人の友人と本の回し読みやビデオの交換などをしてしのいでいました。
楽しかったのは旅行でした。ケルンからオランダやベルギーへは電車で2時間、パリへは4時間くらいでしたから、よく旅行しました。印象に残っているのはギリシャのミコノス島でした。青い海、白い建物、日本では見られない風景に感動しました。
仕事を効率的に進めるためにも、休暇をとってリフレッシュして、人生を楽しむことが大事だということを教えられました。
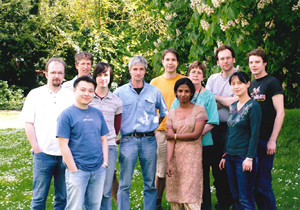
▲ ケルン大学の研究室の仲間と。真ん中のジーンズ姿の男性がマーティン
