───大学ではどんなことを勉強したのですか。
秋田大学は新設2年目で、臨床も基礎も、創世期の意気に燃えた若い教授が全国から集まってきて非常に充実した授業を受けることができました。けれども、神経学の分野が手薄でした。神経内科についてもう少し勉強したいと考えていた5年生のとき、信州大学に神経内科の新しい講座が開設され、東京大学から専門の先生が赴任されるということを聞き、夏休みに2週間、実習に参加させてもらいたいとお願いし受け入れていただきました。ここでは中枢神経系、脊髄や筋肉の病気、たとえば、パーキンソン病や筋萎縮性側索硬化症、筋ジストロフィーなどの患者さんに、学生である私が話を聞いてそれを主治医がフォローする形で診察経験を積むことができました。若い先生方も弟のように私のことを可愛がってくださって、本当に充実した時間を過ごすことができました。
6年生になって将来の進路を考えていたころ、お世話になった信州大学の教授から「大学院はうちの研究室に来るものと思っています」というお手紙をいただき、あれほど敬遠していた信州に戻ってきたのです。
───その信州大学で神経内科の分野を勉強されたわけですね。神経内科に興味を持ったのはなぜですか。
神経内科は患者さんを徹底的に診ることが重要な分野です。患者さんと向き合い、話し合い、診察を重ねるなかで、患者さん自身が病の本質を医者に教えてくれる、そういう病気を対象にしている診療科なのです。これは私に向いている医療分野だと思いました。大学院時代に地方の病院で研修医をして、多くの患者さんを診察してますますその思いを強くしました。
そんな折、東京大学医学部の薬理学教室で筋ジストロフィーを勉強する若手を捜しているから行ってみないかというお話が教授からあり、そこで筋ジストロフィーの生物学的な研究をすることになったのです。今では考えられないことですが、信州大学に籍を置いたままの内地留学でした。
───東大では具体的にどんなことを研究したのですか。
まだ筋ジストロフィーの原因遺伝子が分からなかった時代で、筋ジストロフィーにかかっているニワトリの筋肉を電子顕微鏡で観察したり、すりつぶしてタンパク質がどうなっているのかを電気泳動で調べたりしていました。あるとき図書室で論文を読んでいて、ニワトリの胸筋の発達の過程で変化する重要性に思い至り、そこからタンパク質の異常を発見することができました。この研究で博士号をいただいたのです。
この時期、生活のためもあって月に一度信州の病院で当直医を担当していました。東大最寄のお茶の水駅から長野方面へと向かう鈍行列車に乗って、その月に何をしたのかを思い浮かべるのですが、毎月何らかの発見があり、その都度まるで新しい地平を見ているように自分が進歩していくのが実感できました。研究のスタートは決して早かったわけではありませんが、20代でこのような研究の楽しさを知ることができたことは大きな意味を持っていたと思います。
───臨床医か研究者の道を選ぶか、迷ったことはなかったのですか。
父は開業医をしていて、地域の人から圧倒的な信頼を得ていました。父を見て育っていたので、心のどこかに開業して臨床医をしても、父親を超えることはできないという思いはあったのだと思います。30代前半になって、臨床医になるか研究者になるかの道を決めなければならない時期が来ました。
それまで神経内科の患者さんを診察した経験から、治療できる患者さんもいるけれど、手を尽くしても治すことができない患者さんがいることを思い知らされました。そうした患者さんを治療できるようにするためには、もっと基礎医学や分子生物学的な知識をしっかり身につけなければならない、と考えていました。

▲ スイス・グリンデルワルドのスキー場にて
そんな折、信州大学の恩師から「留学してもいいよ」と言われました。34歳のときで、本当に嬉しかったですね。そこで以前から学んでみたいと思っていたフランスのパスツール研究所に留学しました。
約5年間在籍し、自分で遺伝子を操作したりしながら、筋ジストロフィーの分子遺伝学や病気の成り立ちなどを学んでいきました。
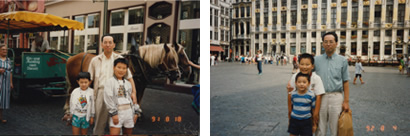
▲留学時代の家族との思い出の写真から。左は旅先のドイツ・ハイデルベルク。右はベルギー・ブリュッセル。
