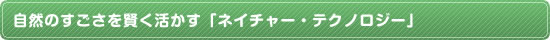その一人が、東北大学の石田先生だ。先生はご自分の研究を「ネイチャー・テクノロジー」と呼んでいる。
「ネイチャーとは動物や植物はもちろんですが、土なども含んだ幅広いものです。そして私は『ネイチャー・テクノロジー』を、生物のまねを越えて、『自然のすごさを賢くいかす』ことだと捉えています」
石田先生が開設しているのが、「すごい自然のショールーム」というホームページだ。そこには、こうした観点から収集した200にも及ぶネイチャー・テクノロジーのデータベースがつくられている。そのうちのいくつかを紹介してもらおう。

▲ ネイチャー・テクノロジーのデータベースがある「すごい自然のショールーム」
(現在は、「ネイチャーテクノロジーデータベース」 http://www.naturetech-db.jp/)
「ヤモリはツルツルした壁を上ったり、天井にはりつき、さかさまに歩いたりできます。こんな離れ業ができるのは、ヤモリの指先に目に見えない細かい毛がびっしり生え、さらにその先端は数百に枝分かれしていて、1本1本は弱いファンデルワース力という弱い分子間力ですが、それが大量の毛によって接着力を高め、どんな面にも自在にはりつくことができるからです。また、毛の生え方に工夫があって少しの力ではがせるようにできている。強力な接着力とかんたんにはがせる仕組みを両立させているんですね」

▲ つるつるした壁にも、自在にはりつくヤモリ
それでは、ヤモリのこうした秘密をどう役立てることができるのだろうか。
「ある素材メーカーと大学の研究チームは、髪の毛より細いカーボンナノチューブを並べて、ヤモリの足の裏の構造を再現して、強力な粘着力とはがしたいときにすぐにはがせるテープを開発しました」
このネイチャー・テクノロジーを応用すれば、垂直な壁を自由自在に動き回れる靴やグローブができるかもしれない。まさに映画「スパイダーマン」そのものだが、建設現場で働く人や災害救助の現場で役に立ちそうだ。こうした容易にくっついたりはがしたりできるものは、ヤモリだけでなく、ヤマゴボウ、タコの足の吸盤なども自然界にはいろいろあるのだそうだ。もう一つ紹介していただこう。

「たとえば、私がお手伝いをした、外壁やキッチンシンクは、カタツムリの殻をヒントにしたものです。カタツムリの殻はいつもぴかぴか光って清潔ですが、その秘密は、殻の表面のキチン質を構成しているいくつかの凹凸構造が、水には濡れやすく、油に濡れにくい性質をもっていることにあります。カタツムリの殻についた油汚れに水をかけてやると、油と殻の間に水が入り込み、油を落とす。その原理をヒントに、汚れの落ちやすいセラミックスを開発したわけですね」

▲ ハスの葉にきれいな水玉ができるのも、葉の表面に、数ミクロンのデコボコがあり、さらにその表面にその数百分の一の突起がついていて水玉がつぶれるのを防いでいるから。表面をつるつるにコーティングするのではなく、まったく逆のしくみだったのだ!
医学分野でもいろいろな例を教えてもらった。すでに実用化されているものとしては、蚊に刺されても痛くない秘密を解き明かしてつくられた、痛みの少ないマイクロ注射針がある。蚊の針の形状をまね、針の太さは50-85マイクロミリメートルと細い。また、猛毒で知られるサソリの毒の構成成分である「スコーピン」は、有害な菌や細菌の増殖を抑え、マラリアのような寄生虫を撃退する働きを持つ。「スコーピン」を研究することで新しい安全な抗菌物質の開発につながるかもしれない。
「モンシロチョウのサナギから取れる0.1ミリリットルの体液を薄めて培養し、胃がん細胞に加えたところ、6時間後に細胞がアポトーシス(細胞が自ら死んでいくこと)を起こすことがわかっています。このサナギの体液はピエリシンというペプチドで、健常な細胞には作用しないことから、抗がん剤の開発が期待できるでしょう」
このような例は無数にありそうだ。なにしろ地球上に存在する種の数は300万種~1億1100万種とも推計されている。自然や生物の営みに、数多くのヒントが潜んでいるのだ。