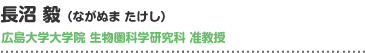SCIENCE TOPICS いま注目の最先端研究・技術探検!
第12回 辺境に生きる生命を手がかりに「生命とは何か」を考究する ~広島大学大学院 生物圏科学研究科 長沼毅准教授を訪ねて
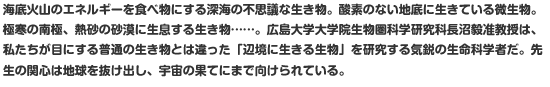
2011年8月、宇宙と地球の生命とを結ぶ興味深いニュースが、米航空宇宙局(NASA)から発信された。それは、「地球上の生命の設計図であるDNAをつくる分子が、地球外にも存在する初めての証拠が見つかった」というものだ。DNAはアデニン、グアニン、シトシン、チミンの4つの分子で構成されているが、南極などで見つかった隕石を分析した結果、そのうちのアデニン、グアニンが含まれていたほか、これらの分子と構造のよく似た炭素や窒素から構成される分子を複数発見したというのだ。地球上の生命を司る遺伝子と同じ分子が宇宙にも存在するとしたら、宇宙にも生命は存在するのだろうか。もし、宇宙にも生命が存在するとしたら、生命はいつ、どこで、どのように誕生したのだろう。
長沼先生はこんな胸がわくわくするような謎を追いかけて、海底、南極、砂漠、地底など、いわば、地球の「辺境」の地域を探索しながら研究を続けている。
先生が辺境にすむ生物に興味を持ったのは、1977年、高校生のころだった。
「当時16歳でしたが、この年、米国の潜水船アルビン号が、ガラパゴス沖の海底で熱水噴出孔を発見し、そこで地上の生物では考えられない不思議な生き物が見つかったというニュースが伝わってきたんです。その生物はチューブワームといい、長い筒型をしていて、大きなものは2メートルもあり、それが熱水噴出孔のそばに群生しているというんです。当時、生命とは何か、生命の起源などについて関心を寄せていた私は、海の底で思いも寄らぬ現象が起き、不思議な生き物が生存しているんだと感動しましたね。チューブワームなどの生き物が深海で見つかったことは、エポックメーキングな出来事でした。それまでは、深海は生命の存在しない死の世界と思われていたのに、多様な生物がいて、生命の営みが行われることが分かり、ダイナミックな深海生命観が生まれてきたからです」

▲ 大西洋の熱水噴出孔(NOAA)

▲ チューブワーム(NOAA)
大学に入学して生物学を専攻した長沼先生は、大学院に進学し、在学中にライフワークとも言える「辺境生物」探検のチャンスに恵まれた。1987年に、日本で初めてとなる熱水噴出孔の調査が海洋科学技術センター(現:海洋研究開発機構=JAMSTEC)で始まり、潜水調査船「かいよう」に乗ることができたのだ。先生はさらに88年にも同船に乗り、太平洋のフィジー諸島付近の深海底調査航海に参加することができた。長沼先生の担当は、大学院で研究していた微生物の調査だった。
「海の底の光景は船から下ろしたカメラで見るわけですが、足元の2000メートル下にはこれまで見たこともない世界が広がっていて、それは感動したな。映像にコシオリエビやシロウリガイなどの深海生物が登場すると、もう、胸が高鳴るわけ。そうこうするうちに、カメラが熱水噴出孔を捉えたんだ。日本チームによる初の熱水噴出孔の発見現場にいたという喜びは格別なものがありました」
この航海の後、長沼先生はJAMSTECに入所、潜水調査船「しんかい2000」に乗って沖縄トラフを探検することになった。
「この深海調査では、カメラの映像を通してではなく、球状の船室に乗り込んで潜り、実際に海底2000メートルの光景を見ることができました。熱水噴出孔にたどり着いたら、そこはチューブワームが山のように群がっていたんです」
高校生のときに、ニュースで知った海底の不思議な生き物が、長沼先生の目の前に現れた瞬間だった。

▲ 無人探査機「ドルフィン3K」の操縦席

▲ 「しんかい2000」に搭乗した長沼先生

▲ 「しんかい2000」
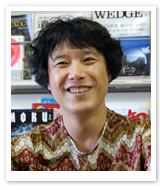
1961年、人類初の宇宙飛行の日に生まれる。1989年、筑波大学大学院生物科学研究科博士課程修了。海洋科学技術センター(現・独立行政法人海洋研究開発機構)、カリフォルニア大学サンタバーバラ校海洋科学研究所客員研究員等を経て、広島大学大学院 生物圏科学研究科准教授。北極、南極、深海、砂漠など世界の辺境に極限生物を探し、地球外生命を追究する吟遊科学者。テレビの番組で「科学界のインディ・ジョーンズ」と紹介された。宇宙飛行士になりたくて試験を受けたことがある。そのとき選ばれたのは野口聡一さんだった。著書に『深海生物学への招待』『生命の星・エウロパ』『辺境生物探訪記』『世界をやりなおしても生命は生まれるか?』など多数。