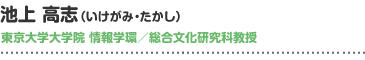SCIENCE TOPICS いま注目の最先端研究・技術探検!
第17回 動きが生命をつくる~東京大学大学院情報学環 池上高志教授を訪ねて~
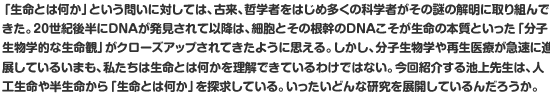
駒場にある池上先生の研究室を訪ねると、先生がまず見せてくれたのは、不思議な映像だった。
5~6つの小さな丸いものがゆっくりと動いている。あるときはお互いに寄り添うように並んで動いては、また離れていく。またあるものは尾のような航跡をあとに残しながら上のほうへ。まるで自由意思を持って動いているようだ。

▲ 油滴の群れの写真
「これは2つの化学物質がつくり出す油滴です。無水オレイン酸というオリーブオイルの主成分をpH11ぐらいの高アルカリ性の水溶液に入れると、水和反応が起こりオレイン酸が生まれます。オレイン酸は疎水基と親水基を持っているので、親水基を外側にして油をぐるっと取り囲むんです。普通ならそれでおしまいですが、表面張力に変化が起きて油滴の表面にそって対流が生まれると、今度は対流が新鮮な油を表面に押し上げ、その反応が起きるところを先頭として、溶液中を勝手に止まったり曲がったりしながら進んでいくのです。だいたい20分ぐらいもすると止まってしまいますが、これを見ているとまるで生命がそこにいるようでしょう?」
油滴の大きさは0.2ミリメートルくらいだが、大きさによっても動きは違う。pHの差を検知して逆に動くこともできるし、一世代だけなら自己複製できるものや、2種類の油滴のうち、片方がどんどん増えて世界を占めていくようなものも見つけたのだという。
「動くためにはエネルギーが必要で、この場合は化学反応がエネルギーです。生命の本質が非平衡状態をつくることにあるとすると、この油滴は非平衡状態を自分でつくりながら動き出すシステムというわけですね」
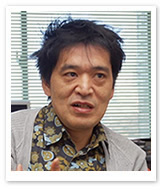
1961年長野県生まれ。84年東京大学理学部物理学科卒業、89年同大学院理学系研究科博士課程修了。同年米国ロスアラモス国立研究所に留学。90年神戸大学大学院自然科学研究科助手。94年東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻助教授に。同年オランダ・ユトレヒト大学理論生物学招聘研究員などを経て、2008年東京大学大学院総合文化研究科教授。2010年より現職。理学博士。複雑系と人工生命をテーマに研究を続けるかたわら、アートとサイエンスの領域をつなぐ活動も精力的に行う。音楽家・渋谷慶一郎とのプロジェクト「第三項音楽」や、写真家・新津保建秀とのプロジェクト「MTM」をはじめ、活動は多岐にわたる。著書に『生命のサンドウィッチ理論』、『動きが生命をつくる―生命と意識への構成論的アプローチ』、『複雑系の進化的シナリオ』(共著)など。