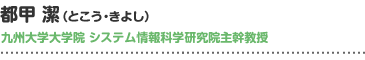SCIENCE TOPICS いま注目の最先端研究・技術探検!
第21回 味覚やにおいなど、五感を計測するセンサーづくりに挑む~九州大学大学院・システム情報科学研究院 都甲研究室を訪ねて~
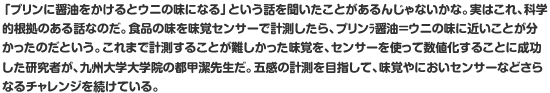
近代の科学は、この世界を次々に数値化してきた。古代の人々なら何かの祟りと感じただろう台風の勢いはヘクトパスカル、地震のエネルギーの大きさはマグニチュードで表される。私たちのからだの状態だって例外ではない。血圧、体温、脈拍などはもちろんのこと、視覚、聴覚、あるいは知能まで測定し、IQという数値で表現することに成功してきた。
ところが、味覚については長い間、正確な測定方法が見つからず数値化することが難しいと考えられてきた。この問題に挑戦し、味覚を数値化する味覚センサーの開発に成功したのが都甲先生である。
そもそもいったいどうして味を測定しようと考えたのだろう。
「ま、話半分に聞いてください」といたずらっぽく笑いながら、先生が話すその動機とは——。
「私はずっとニンジンが嫌いだったんです。あるとき妻がつくってくれたハンバーグがとてもおいしかった。『今日のハンバーグはおいしいね、どうしてだろう』と聞いたところ『あなたの嫌いなニンジンを小さく刻んで入れてある』と言うんです。それで、人間の味の感じ方とは、ずいぶんあいまいなものなんだなと思いましたね。それは味を測るモノサシがないからではないか、ならば味を計測できる味覚センサーをつくってやろう、そう考えたんですよ」
今からおよそ30年前に味覚センサーをつくろうと考えた都甲先生だったが、実はそれまでに「味を測る」研究がなかったわけではない。比較的早いころから果物などにどれだけの糖分が含まれているかを、糖分の濃度によって光の屈折率が違うことを利用して計測する糖度計が開発されていた。また1970年代には、バイオセンサーを使って、食べ物にどれだけアミノ酸やグルコースなどの化学物質が含まれているかを測定しようという研究が行われていた。けれども、味に関係する化学物質は何十万とあるから、この方法では膨大な手間がかかってしまい現実的ではなかった。しかも、コーヒー、砂糖、ミルクなど、それぞれの食品にどれだけの化学物質が含まれているのかは分かっても、それらをミックスしてどんな味になるのかは測定しようもない。ましてや、肉と野菜を一緒に煮込んだシチューの、それぞれの材料の相乗効果となると、センサーでは検出しようがない。
そもそも味覚とは個人的なもので、同じ料理を食べても、感じ方は人それぞれ。しかも舌で感じる味と、脳で感じる味も一様ではなさそうだ。先生が採用した方法はどんなものだったのだろう。
味覚の基本要素
| 味 | 代表的な物質 | 生理的な意味 | |
|---|---|---|---|
| 基本の5つの味 | 甘味 | ショ糖、ブドウ糖、人工甘味料 | エネルギー源 |
| 塩味 | ナトリウムイオンなどの金属系陽イオン | ミ体液バランスに必要なミネラルの補給 | |
| 酸味 | 酢酸 塩酸 クエン酸など酸が解離してできた水素イオン | 新陳代謝の促進 、腐敗のシグナル | |
| 苦味 | カフェイン キニーネなどアルカロイド系物質 | 毒性の警告 | |
| うま味 | グルタミン酸ナトリウム イノシン酸ナトリウム | 生物に不可欠なアミノ酸、ヌクレオチド類(核酸のもと)の供給 | |
| その他 | 辛味 | カプサイシン、アリシン | 舌や口腔内への物理的刺激。温度を検知する感覚細胞の応答による、熱さ・痛みに類似した感覚。 |
| 渋味 | タンニン系の化合物 | 口腔粘膜が縮むような感覚のため収斂味ともいう。渋みの元となる物質が、さまざまな感覚受容体タンパク質に非特異的に結合することでもたらされる。 | |
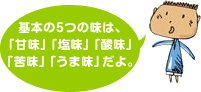
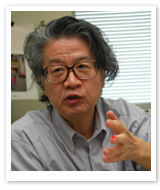
1975年九州大学工学部電子工学科卒業。80年同大学大学院工学研究科博士課程単位取得。
工学部助手。90年同大学工学部助教授。96年同大学大学院システム情報科学研究科助教授。97年同研究科教授に。2000年同大学院システム情報科学研究院教授。08年同大学院システム情報科学研究院長。09年より現職。著書に「プリンに醤油でウニになる」「味覚を科学する」など多数。2013年紫綬褒章を受章。