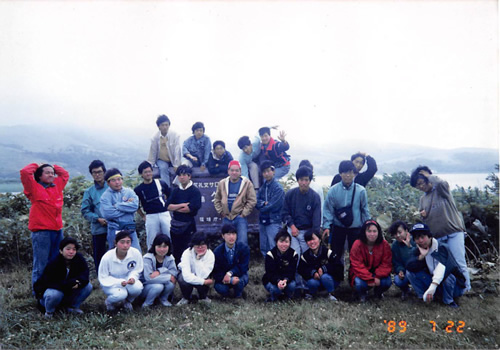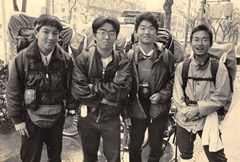───生物への興味は持っていたんでしょうか。
ええ、子どもの頃は周りにまだ自然が残っていましたので、春にはオタマジャクシを捕まえたり、夏にはトノサマバッタやイナゴを捕ったり、秋にはオオカマキリやコオロギを捕まえて家で飼ったりしていました。残酷なこともしていましたよ。小学校2年生の時のことです。放課後に友達何人かとカエルを捕まえに行って、そのうちの一匹をみんなの前で解剖しちゃったんです。「ここが腸、ここが肺」なんて言いながらバラバラにしたんですが、そのことを得意になって担任の林幹夫先生に報告したところ、「カエルにも命があるんや!遊び半分で命を殺めるな!!」とこっぴどく怒られました。林先生には命の尊さを教えてもらったことを感謝しています。
その後、子どもらしい残酷さは息をひそめましたが、生き物への興味は失せることなく、むしろますます盛んになっていきました。小学校高学年になると、生駒山の近くにある飯盛山へコガネムシやカブトムシなどの幼虫を捕りに行きましたね。幼虫が蛹に変態して成虫になるのを観察するのが楽しかったです。なんであんなにも形が変わってしまうのか不思議でなりませんしたから。でも、このような生物への興味はなぜか中学生になると全く失ってしまいました。先述したようにバイクに、もっと言えばそのエンジンの仕組み(機械仕掛け)に興味を持つようになったからです。
───すると、生物学に再び興味を持つようになったのはいつなんですか。
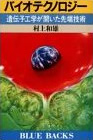
▲ 生物学の面白さを教えてくれた一冊
高校1年の時、国語の清野先生が「最近は新聞紙上でよくバイオテクノロジーという言葉を見るようになりましたね。皆さんどういうテクノロジーか知っていますか?」と雑談しながら教えてくれたんです。そこでその日の下校時に本屋に立ち寄って見つけたのが、村上和雄先生が書いた『バイオテクノロジー 遺伝子工学が開いた先端技術』という本。
この本を読んで「生物とは機械だな」と思いました。まず遺伝子という設計図があって、その設計図通りにタンパク質が出来上がる。しかも、大腸菌から人までありとあらゆる生き物が同じ分子の文字で設計図が書かれているというのを初めて知りました。さらに私自身疑問に思ったのが「誰がその設計図を描いたんや?」です。「いやー、生物学っておもろい!」と目からうろこが落ち、すっかり生物学にはまりましたね。
それで、2年生の進路分けにあたっては国立理系コースを選択しました。受験科目では生物、化学を選択したのですが、生物の伊藤隆先生がとても一生懸命で、私の度重なる突飛な質問に一つひとつ真剣に答えてくれたことで、ますます生物学が好きになりました。
───もうそのときは、大学で生物学を専攻しようと考えていたのですか。

▲ 北海道網走にて
そうです。当時、関西で生物学を学べる大学は少なく、京都大学、大阪大学、神戸大学、甲南大学くらいしかありませんでした。その中で、京都大学は理学部として数学、物理、化学、生物を一括りにして300名もとるそうなので、入りやすいだろうと安易に考え京大を目指しました。でも、あえなく敗退して浪人することに。
ところが、父親は「大学なんか行ったら頭でっかちになるだけで何にも役に立たん。手に職をつけろ」と大学進学には大反対でした。「大学に行くつもりなら学費は自分で稼げ」と突き放されたので、受験に失敗してすぐに倉庫で荷物運びのアルバイトを始めました。昼は家で勉強、夕方から夜はアルバイトという生活が数カ月続きました。するとだんだんそういう生活にも飽きてきてしまい、たまったアルバイト代で50㏄のバイク(ヤマハJOG)を買って、北海道へ旅に出ました。実は北海道へと渡るフェリーの中でラブロマンスが生まれたりとイイ話がいっぱいありますが、長くなるので割愛(笑)。
旅から戻って秋からは本格的に勉強を始めて、筑波大学の生物学類に合格することができました(京都大学はまたもや不合格・・・)。筑波大学では1、2年生は大学の宿舎生活となり、必然的に密接な交友関係ができて、恋愛や人生や学問のことなどを毎日のように夜遅くまで語らい合いました。その一方で、大学時代にしかできない勉強以外のことにも積極的にチャレンジしました。お蔭で人間として大きく成長できたと思います。

▲ 冬山単独行。赤岳山頂にて