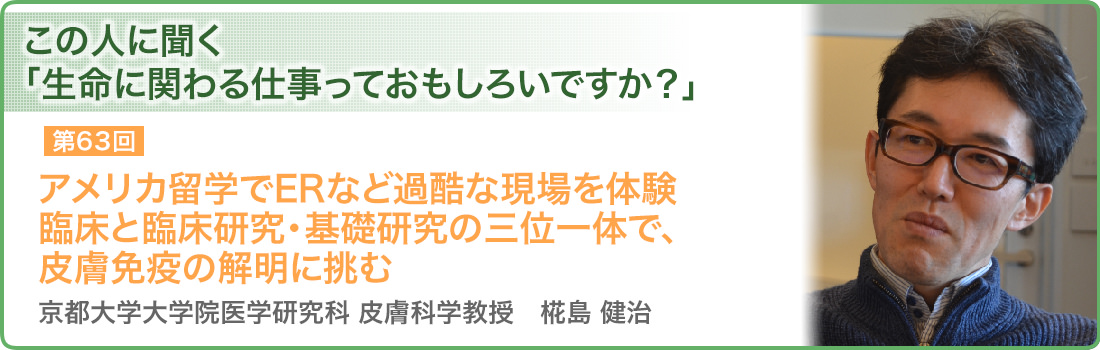profile
椛島 健治(かばしま・けんじ)
1970年岐阜県生まれ。96年京都大学医学部を卒業後、横須賀米海軍病院でインターン。97年ワシントン大学医学部附属病院に臨床留学。2003年京都大学大学院医学研究科博士課程修了。その後、同大学医学部附属病院助手、カリフォルニア大学サンフランシスコ校医学部免疫学教室リサーチアソシエイトを経て、05年産業医科大学皮膚科准教授。08年京都大学医学研究科創薬医学融合拠点准教授。10年同大学医学研究科皮膚科准教授。15年より現職。趣味は40歳から始めたマラソンで、現在も42.195㎞を3時間以内で走るサブスリーをキープ、トレイルランニング100マイルレースも多数走破。ブログ「洛中洛外から椛島健治の頭の中を送ります」更新中。
研究室HP:https://dermatology.kuhp.kyoto-u.ac.jp/
ブログ:https://kenjikabashima2.com/
町に1人しかいない開業医の献身的な姿を見て医師をめざす
———医学部に進もうと思ったのはいつごろで、どんなきっかけからですか?
父親が転勤族だったのであちこちに引っ越したんですが、一番長く住んで、育った場所といえるのは福岡です。北九州市の小倉の外れに家があって、道路の信号機が町全体で1個しかないような田舎でした。開業医の先生が町に1人しかおらず、その先生が昼夜問わず地元の人たちを診療していてとても尊敬していました。その先生を見ているうちに、子どものころから、医者って人の役に立つ大事な仕事だな、将来は医者になりたいなと思うようになったんです。
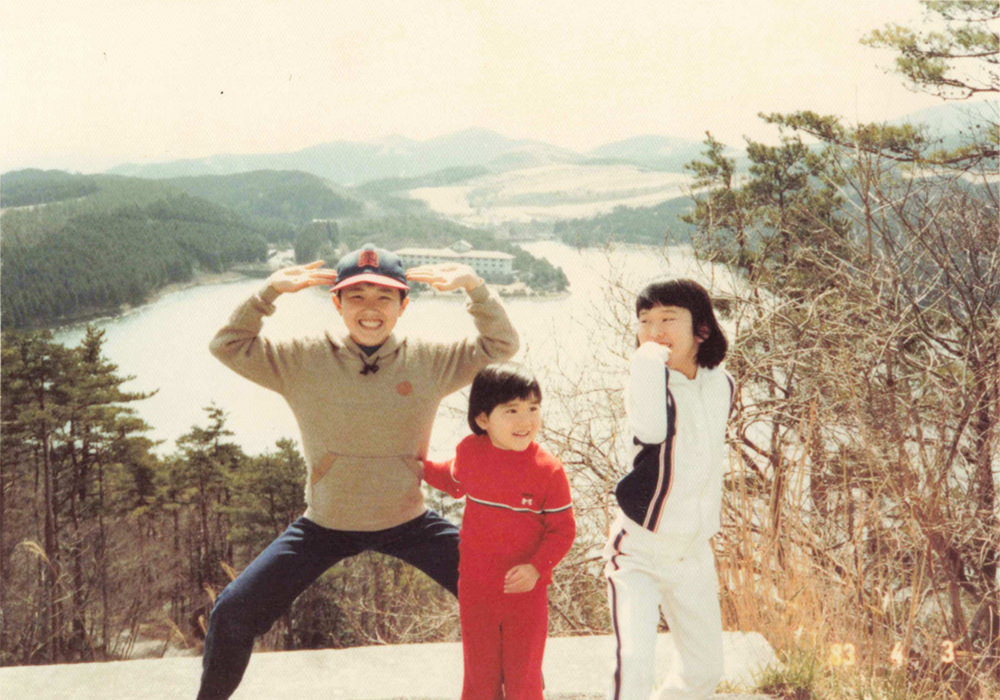
2人の妹と。ジャッキー・チェンがはやっていたころ
———京都大学を志望した理由は?
京都大学の自由な学風に憧れたことが一つ。それと下宿もしたかった。小倉高校と横浜の柏陽高校、千葉高校と3つの高校に通ったのですが、高3のときは千葉でしたから、東京あたりの大学だと自宅から通うことになってしまう、それはイヤだな、と。

京都への修学旅行。このとき京都の街に魅せられて京大を意識した
———どんな高校生でしたか?
外で遊ぶのが好きで、野球をやったりもしていましたが、本を読むのも好きでした。授業で学ぶよりむしろ自分で選んだ本から学んだことの方が大きかった気がします。トーマス・マンの小説とか、ガモフ全集、「ロウソクの科学」、ファインマンの物理学の本…、英語も原著の小説を読んで勉強したりしました。
現役合格できずに浪人したんですけど、浪人中も塾や予備校には行かなかったんですよ。いわゆる宅浪。自分で足りない勉強をやっていくのが性に合っていたんですね。
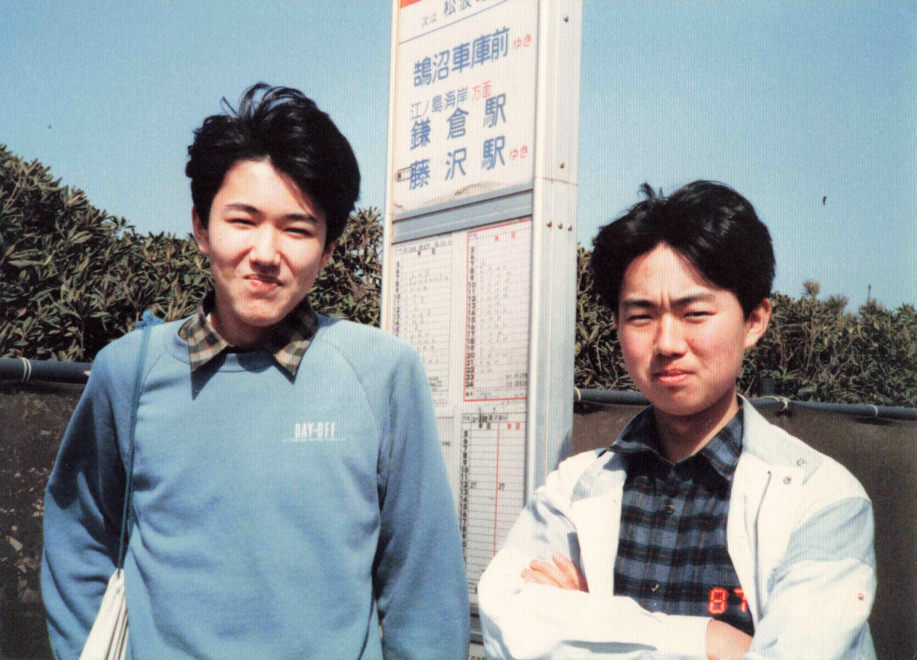
転校先の茅ヶ崎まで小倉高校の友人(右)が遊びに来てくれた

高校一年時。囲碁に没頭したが、そんなに才能はなかった(右手前)
———当初から研究者になることも視野に入れていたのですか?
開業医の先生を見て医者になることをめざしたわけですが、京大の医学部を受験するころには、医学部はもちろん医者を養成するところだけれど、病気の原因を解明する研究もしているということがわかってきて、臨床と研究の両方をやって病気を治す新しい薬をつくったりできればもっといいなと漠然と考えていましたね。
臨床と研究とを両立させるためには早めに研究のイロハを学んでおいた方がいいと、学部3年のときから研究室に入り浸っていたんですよ。
———どんな研究室ですか?
アレルギーにかかわるIgE受容体の研究をしている淀井淳司先生(当時京大ウイルス研究所生体応答学研究部門・感染防御教授)の研究室です。
そして4年生のときには、サマー・スチューデントとして3カ月半ほどアメリカのNIH(国立衛生研究所)での研究を体験したり、アイオワ大学でアメリカの医学部の授業に参加させてもらったりしました。
———NIHといえば、アメリカで一番古い、由緒ある医学研究の拠点ですが、どんな思い出がありますか?
研究の体験がすごく楽しかったですね。日本での研究も楽しかったけれど、学生にそんなにチャンスを与えてくれるわけではありません。ところが、ぼくが行ったNIHのラボはウイルスの研究をしているところで、ボスはジョヴァンナ・トサト(Giobanna Tosato)というイタリア人女性でしたが、実験の結果を持っていくとやたらとほめてくれるんです。「すごい!よくそんなことを思いついたね」などとおだてまくってくれて、自分で考えて取り組むことの大切さを教えてもらった気がします。

NIHでのサマー・スチューデントでお世話になったGiobanna Tosato博士との再会。30年前と変わらないお元気さ! ボストンマラソンも10回ほど完走されているつわものです!
———アイオワ大学ではいかがでしたか?
アイオワ大学では、自分と同じ医学部の3年生と一緒に授業を受けました。それが人生の大きな転機の一つとなりましたね。
———いったい、どんな授業だったんですか?
日本での医学の勉強というのは、例えば胃がんだったら胃がんについての講義、解剖なら解剖実習といった具合ですが、アメリカの医学部の教育は、早い時期から模擬患者を使って、どういうふうに治療していくべきかをグループディスカッションするなど、実践的に学んでいくんです。ぼくもディスカッションに参加しましたがまったく歯が立たなかった。そこで、将来、臨床医としてやっていくのなら、日本だけでなくアメリカの臨床システムも経験しておく必要があると考えるようになったんです。

アイオワ大学へのサマー・スチューデント。Yamada Thoru先生(現・神経学名誉教授)を訪ねて