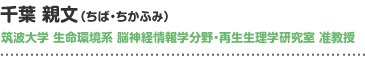SCIENCE TOPICS いま注目の最先端研究・技術探検!
第31回 イモリの体再生のメカニズムを分子レベルで解き明かし、人の医療に応用したい~筑波大学 再生生理学研究室・千葉親文准教授を訪ねて~
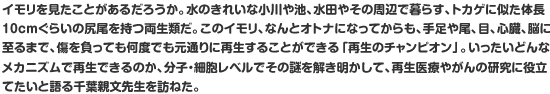
野原で野生のトカゲに出会って、捕まえようとトカゲのしっぽを掴むと、トカゲはしっぽを切って逃走してしまう。しっぽは3週間ぐらいで再び生えてくる。「トカゲのしっぽ切り」という諺は、トカゲのこの生態にちなんでいて、悪事を働いたエライ人が下っぱの人間に罪をかぶせて生き延びること。諺になるくらいだから、トカゲがしっぽを再生する能力は昔から知られていたに違いない。
ただし、トカゲの場合、しっぽが再生するのは一度きり。ところが、しっぽがちぎれても何度でも生えてくるのがイモリだ。トカゲに姿かたちが似ているけれど、トカゲは爬虫類で、イモリは両生類という大きな違いがある。さらに、その再生能力が半端ではない。しっぽのほか、足やアゴも再生する。目について言えば、レンズを19回摘出しても元通りになったという記録がある。心臓だって心室を部分切除しても再び心臓の働きを取り戻す。脳の一部でさえ再生するというのだから何ともすごい! こんなタフな再生能力を持っているため、イモリは「再生のチャンピオン」と呼ばれているのだ。
イモリの再生能力の高さについてはかなり以前から知られていた。すでに1769年には、実験動物学の祖と言われるイタリアのラザロ・スパランツァーニが、「なぜイモリだけが、このように卓越した再生能力を持つのか?」と、疑問を投げかけている。しかし、以後250年近く、その謎は解明されてこなかった。分子生物学が急速に進展して以降も、はかばかしい進展はなかった。イモリのゲノムはヒトの5~10倍と長いうえ、遺伝子改変イモリをつくるのはむずかしく、さらに野生のイモリが準絶滅危惧種に指定されるなど、イモリを実験動物とするのにさまざまな困難があったからである。その困難にチャレンジし、イモリの四肢再生のヒミツを分子レベルで解き明かしたのが千葉先生だ。

▲ アカハライモリ
2対4本の短い足と長い尾をもつ。背中側は黒っぽい地味な色だが、腹はあざやかな赤地に黒の斑点。意外に皮膚はザラザラしてる。2006年に環境省のレッドデータブックで準絶滅危惧種に指定された
写真提供:千葉親文准教授
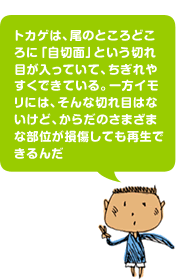
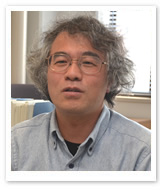
1965年福島生まれ。89年奈良教育大学教育学部卒。92年同大大学院教育学研究科修了。筑波大学に移り、神経生理学のノウハウを活かして、アカハライモリの研究を始める。95年筑波大学大学院生物科学研究科修了、博士(理学)。同大学生物科学系助手に就任。96年同講師、2006年大学院生命環境科学研究科助教授。11年より現職。イモリ研究者でつくるイモリネットワーク代表。