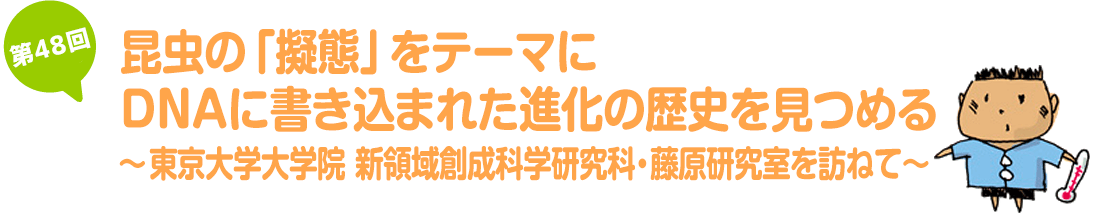何度見ても枝にしか見えない!
新型コロナの感染拡大で「ステイホーム」が呼びかけられるなか、近くの公園を散歩するのが日課になった。そんなときに出合ったのが、葉っぱの上の折れた小枝だった。

おや?と思って近くでまじまじ見ると、何やら脚のようなものが! つついてみたら真っ二つに分かれて、片方が翅をパタパタさせていた。なんと、交尾している最中だったのだ。

散歩から戻って調べてみたら、ツマキシャチホコという蛾であるらしい。
別の日にも、今度は1匹だけちょこんと葉の上にいた。それにしても、何度まじまじと見ても枝にしか見えない。実に巧妙だ。

それ以来、いつもより時間をかけて公園の草むらをサーチしていたら、いるわいるわ。枝にそっくりなヤツや、葉にしか見えない蛾。ノイバラの花の陰にいたのは、まるで鳥の糞!

小枝に擬態したエダシャクガの幼虫。つついてもびくともせず、枝になりきっていた

一見すると、枯れ葉か花びらに見えるヤマトカギバ

木目模様の蛾。まるで樹皮の一部が丸まっているみたい!ハマキガの一種だろうか

翅を閉じていると、樹皮と見分けがつかないルリタテハ

翅を広げたルリタテハは、紺の地色にルリ色のラインが美しい

ゴミを背負っているようなクサカゲロウの幼虫。アブラムシの死骸などの食べかすを背負いカモフラージュしているそうだ

迷彩柄の翅をステルス飛行機みたいに広げたウンモンスズメ

ノイバラの花の陰で胸部を曲げて動かない深緑色と白色の鳥の糞のような幼虫。オカモトトゲエダシャクの幼虫だろうか
がぜん、昆虫の擬態に興味を持っていろいろ調べたところ、千葉県柏市にある東京大学大学院新領域創成科学研究科の藤原晴彦先生が、「擬態・変態・染色体」というキャッチフレーズで、30年以上にわたって昆虫の擬態について研究していることがわかった。「もっと擬態について詳しく知りたい!」と藤原研究室を訪ねた。
「そもそもどうして昆虫は擬態するんですか?」
さっそく質問をぶつけると、「多くの場合、鳥など他の動物から食べられないようにするためですね」と藤原先生。
擬態とは、ある生物が何かに似せて他の生物をだますことで、昆虫だけでなく多くの動物にも見られるが、とくに昆虫ではさまざまなタイプの擬態があるという。
最も多いのは、天敵に食べられないように、葉や枝、幹など、まわりのものに色や形を似せて、見つかりにくくする手法で、これは「隠蔽型擬態(カモフラージュ)」と呼ばれる。

ムラサキシャチホコ。翅はカールしているのではなく、なんと色の濃淡によって枯葉が丸まったかのように立体的に見せているのだ!
毒のある昆虫やハチなどの危険な生物に姿形を似せる擬態もよく見られる。例えば、花を訪れて蜜を吸うハナアブの中にはハチそっくりの姿形をしたものがいて、怖い毒針を持つハチに擬態することで天敵に食べられないようにしているのだ。また、毒のあるジャコウアゲハや、苦くて臭いテントウムシなどに擬態して身を守る戦略は、記憶力のよい鳥に食べられないために効果的だという。この手の擬態は、発見したイギリスの博物学者の名前をとって「ベイツ型擬態」と呼ばれる。自らを目立たせることで難を避けようとする「標識型擬態」の一種だ。

ハナアブの仲間のホソヒラタアブもハチそっくり

ハチに擬態したホリカワクシヒゲガガンボ

ガなのに翅は透明。黒色で腹部に黄色の帯があるコスカシバはドロバチに擬態しているといわれる

テントウムシそっくりに擬態しているキボシマルウンカ。テントウムシは異臭と苦い液を出すので鳥が嫌うという
一方、食べられまいと擬態するのではなく、獲物をおびき寄せるために擬態するタイプもある。東南アジアに生息するメスのハナカマキリはランにそっくりで、花びらのような脚と鮮やかな色をした体を持ち、近寄ってきた昆虫を食べる。これは「攻撃型擬態」とか、この擬態を研究した学者の名にちなんで「ペッカム型擬態」と呼ばれる。

ランの花そっくりのハナカマキリのメス
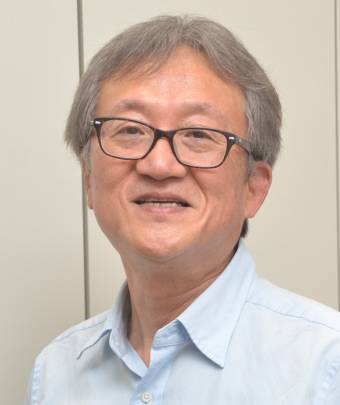
藤原 晴彦(ふじわら・はるひこ)
東京大学大学院新領域創成科学研究科
先端生命科学専攻 遺伝システム革新学分野 教授
1957年兵庫県生まれ。81年東京大学理学部生物化学科卒業。86年同大学大学院理学系研究科生物化学専攻博士課程修了。理学博士。86年厚生省国立予防衛生研究所(現感染症研究所)研究員。89年東京大学理学部生物学科動物学教室講師。92年ワシントン大学(シアトル)動物学部客員研究員。95年東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻助教授。99年同大学大学院新領域創成科学研究科先端生命科学専攻助教授。2004年4月より現職。専門は擬態と変態の分子機構、テロメアと利己的遺伝子の進化など。