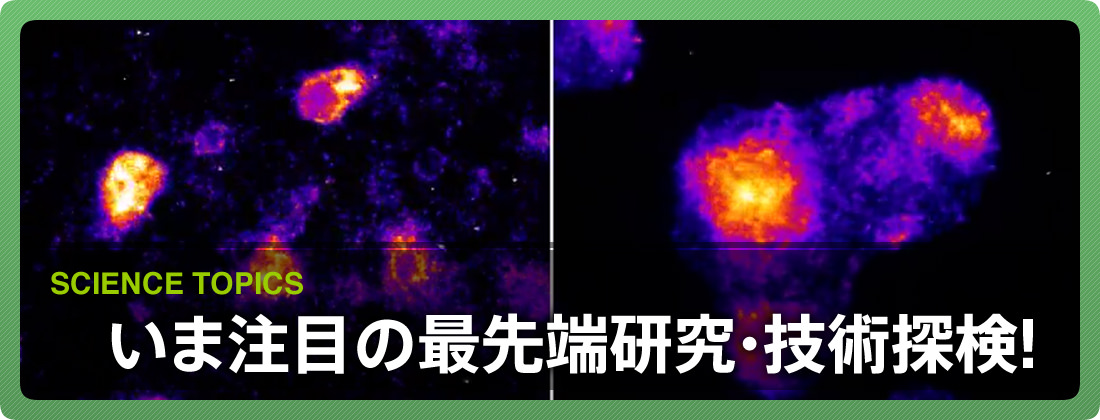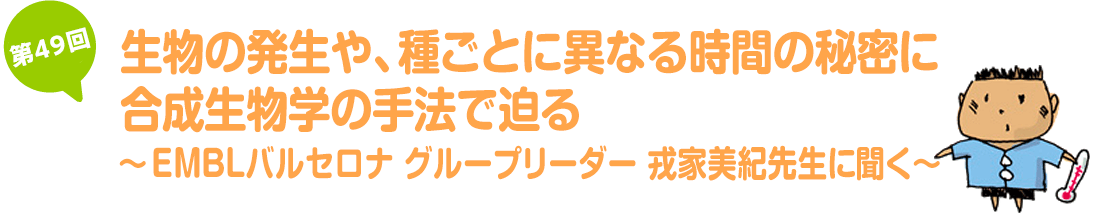生物のサイズによって流れる時間が違う!?
今から四半期以上も前の1992年、ある生物学の新書がベストセラーになった。「歌う生物学者」として有名な、東京工業大学名誉教授・本川達雄先生の『ゾウの時間ネズミの時間』である。
私たちは1日24時間、地球上に暮らす生き物には同じ時間が流れていると考えがちだが、ちょこちょこ動くネズミとゆったり動くゾウ、それぞれの体の大きさによって、心臓が拍動する間隔や呼吸周期、妊娠期間や大人になるまでの時間、寿命などの時間は違い、おおよそ体重の1/4乗(体長の3/4乗)に比例するというのである。大きいものほど時間がかかる。たとえばネズミの妊娠期間は20日間ほどだが、ゾウは約2年だ。寿命にしてもネズミは数年しか生きないが、ゾウの中には100年近く長生きする個体もいる。その一方で、ネズミもゾウも、一生のうちに心臓がドキドキ打つ回数は 20億回と変わらない。
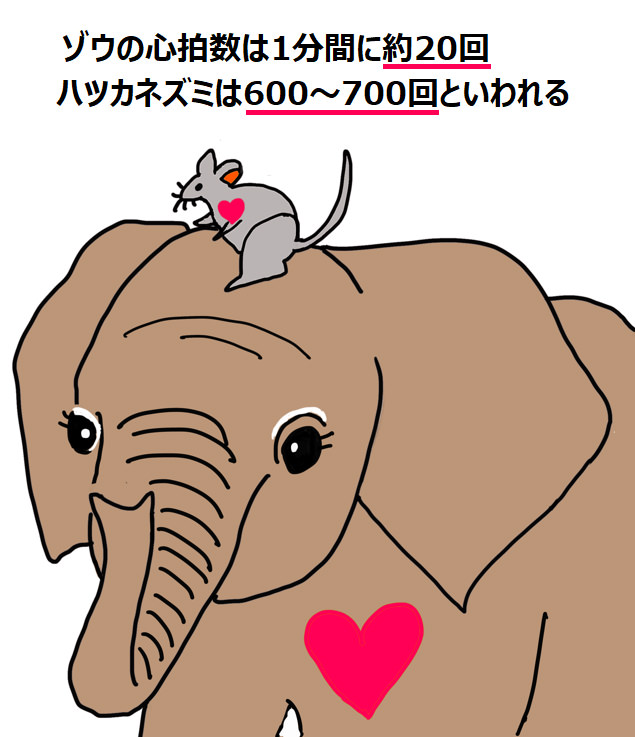
ネズミ君の心臓のドキドキは、ボクよりずっとはやいんだね!
ということは、生き物にはそれぞれ違う時間が流れているといえそうだ。でもその一方で、心臓の拍動を時計と考え、20億針刻んで生涯を閉じるとすると、一生の長さの感覚はネズミもゾウも同じなのだろうか? 時間って何だろう…??
生物学的な関心と、哲学的な気分がないまぜになって、知的好奇心を大いにかきたてられた本だった。
本川先生の著書を思い出したのは、この9月に「ヒトの時間ネズミの時間」という副題が付いたニュースリリースを目にしたからだ。欧州分子生物学研究所(EMBL)バルセロナのグループリーダーを務める戎家美紀先生らのグループが、ヒトの発生時間がマウスより遅いのは、遺伝子発現やタンパク質分解などの速度がヒトはマウスに比べて遅いためだということを、マウスのES細胞とヒトiPS細胞からオルガノイド(ミニ臓器)を培養皿上でつくり出して比較することによって明らかにしたのだ。
戎家先生は、合成生物学のアプローチで発生の謎を探究している研究者だ。いったいどのように研究を進め、発生の時間の謎に迫っているのだろう?もっと詳しい話を聞きたい!と、Zoomでお話をうかがった。

戎家 美紀(えびすや・みき)
欧州分子生物学研究所(EMBL)バルセロナ グループリーダー
2003年京都大学理学部卒業。08年同大学大学院生命科学研究科博士課程修了。09年京都大学生命科学系キャリアパス形成ユニット・グループリーダー。13年理化学研究所発生・再生科学総合研究センター・ユニットリーダー。13-16年JSTさきがけ研究者(兼任)。18年より欧州分子生物学研究所(European Molecular Biology Laboratory=EMBL)バルセロナのグループリーダーとしてスペイン・バルセロナ在住。13年度文部科学大臣表彰若手科学者賞。19年第1回輝く女性研究者賞(ジュン・アシダ賞)。専門は発生生物学、合成生物学。