中高校生が第一線の研究者を訪問
「これから研究の話をしよう」
第5回
生物の機能を活用した、
新しい原理で動く機械の開発
第1章
高校生からの研究紹介
――ヒトデの自己認識システムの解明
- 吉岡
- 吉岡初花です。私たち3人は、「イトマキヒトデの自己認識システムの解明」というテーマで研究をしています。ヒトデは、切断した腕を釣り糸で縫うと再接合することが検証実験で分かっています。しかし、他のヒトデから腕を移植しようとするとうまく接合しないため、どのように自己を認識しているのかという疑問が湧き、研究を始めるようになりました。
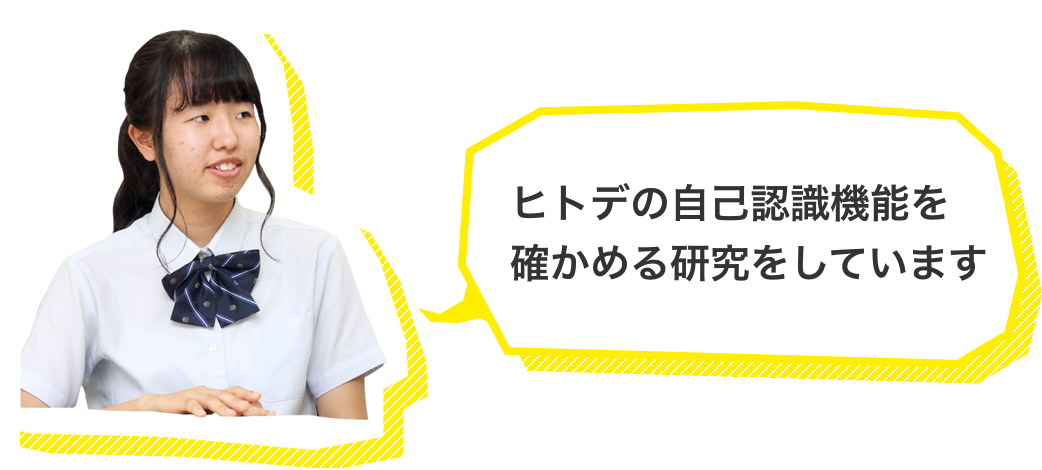
吉岡初花(よしおか ういか)さん(高校3年)
- 田中
- すごく面白いですね!具体的にはどのような実験をしているんですか?
- 吉岡
- 実験では、ヒトデの腕を切断し、釣り糸で縫いつけます。その後、水槽に戻してから数日間放置して、再接合の状況を観察します。ヒトデ自身の体調によって、くっつくかどうかに差が生じるんですけど、きちんと飼育していれば、ほぼ100%くっつくことが検証実験で分かっています。しかし、他個体間で入れ替え実験を6回行ったのですが、一度しか接着することができませんでした。そのため私たちは、ヒトデは自己の腕を認識していて、別のヒトデの腕は接合できないのではと考えています。

ヒトデの腕を糸で縫っている様子

インキュベーターの中で、ヒトデの飼育を行っている
- 田中
- 太畑さん、都藤さんは、この研究を一緒にやっていて、どういう瞬間に楽しいと思いますか?
- 太畑
- 実験を始める前にイトマキヒトデについて調べたときに、腕がちぎれても再生可能とか、切断した腕をくっつけることが可能と書いてあるんですけど、その具体的な方法などはインターネットや本で調べてもまったく書かれていませんでした。そこで、自分たちでステープラーや接着剤など、いろいろな方法での接合を実験したんです。その結果、釣り糸で縫うのが一番いいっていうことが分かったときは、達成感というか、分かってないことを明らかにすることができて嬉しかったです。
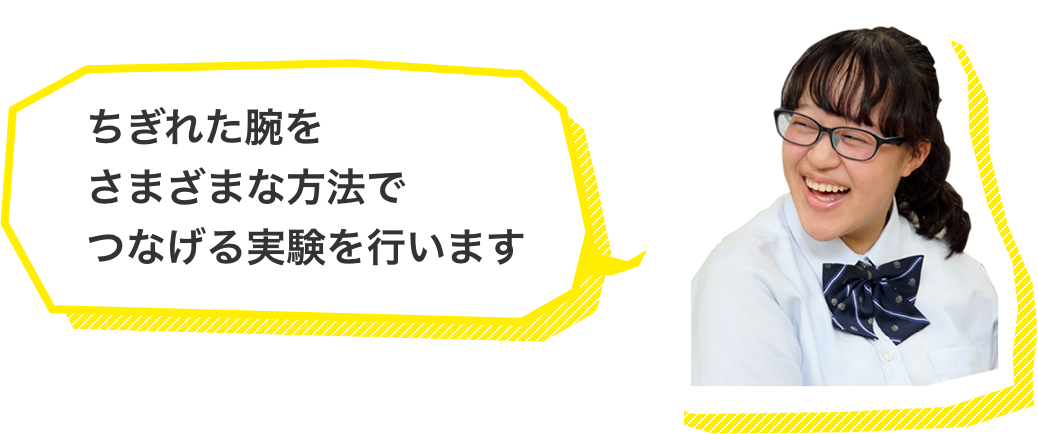
太畑花菜(おおはた かな)さん(高校3年)
- 都藤
- 私は実験の中でも、ヒトデの腕を切って縫う作業を担当しています。なので、実験を行って、くっついていく過程を見ることがすごく楽しいです。
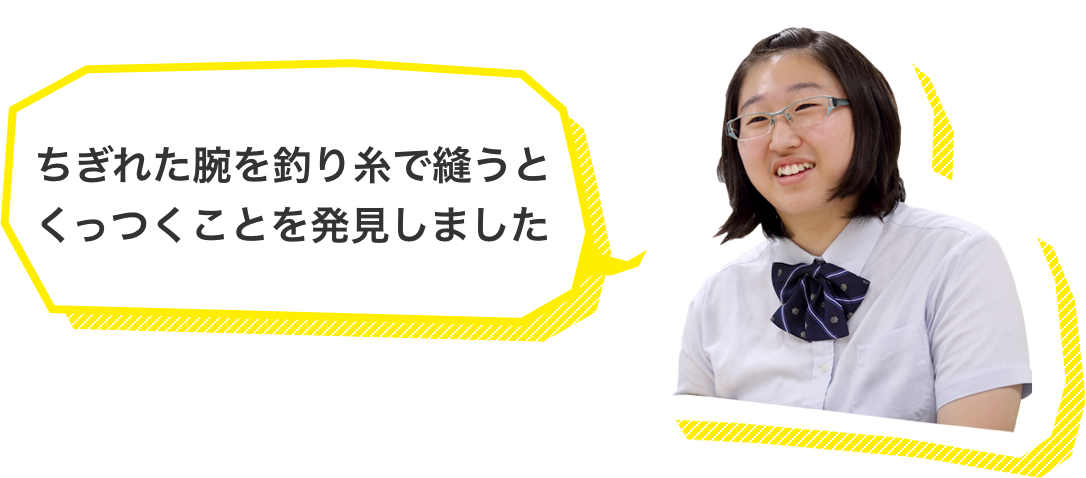
都藤 晴香(つどう はるか)さん(高校3年)
- 田中
- 縫い方にコツなどはあるんですか?
- 都藤
- しっかり固定できるように、けっこう力を入れて縫います。1回1回、玉止めもします。
- 田中
- 器用さが求められるんですね。
- 都藤
- ヒトデの実験で質問なのですが、腕を切断してくっつけようと思うと、すごく動くので固定するのが難しいんです。固定方法として良いアイデアはありますか。
- 田中
- 同じようなことを僕の研究室でもやっていますよ。でもスケールはもっと小さくて、細胞レベルです。細胞もよく動くので、細胞が外に出ないような壁を作っています。それと同じように、ヒトデの形に合ったサイズの型を作って、そこにはめ込むとよいかと思いますよ。5本の腕のうち1本だけを開放しておくことで、その腕だけを対象に実験ができますよね。
- 都藤
- なるほど、ありがとうございます!次の実験で実践してみたいと思います。
- 田中
- ちなみに、なぜヒトデを研究しようと思ったんですか。トカゲとかイモリとか切っても再生する動物って他にもいそうな気もしますけど。
- 吉岡
- もともと再生医療に興味があって、再生する生き物について調べようと考えました。学校の近くに海があるので、海の生物の中で再生するものを調べて、ヒトデに決まりました。周りの海に比べてきれいな兵庫運河でヒトデを採取しています。
- 田中
- なるほど。対象が身近にいて手に入りやすいというのは、研究を進める上で重要ですね。では次に、私の研究を紹介しましょう。