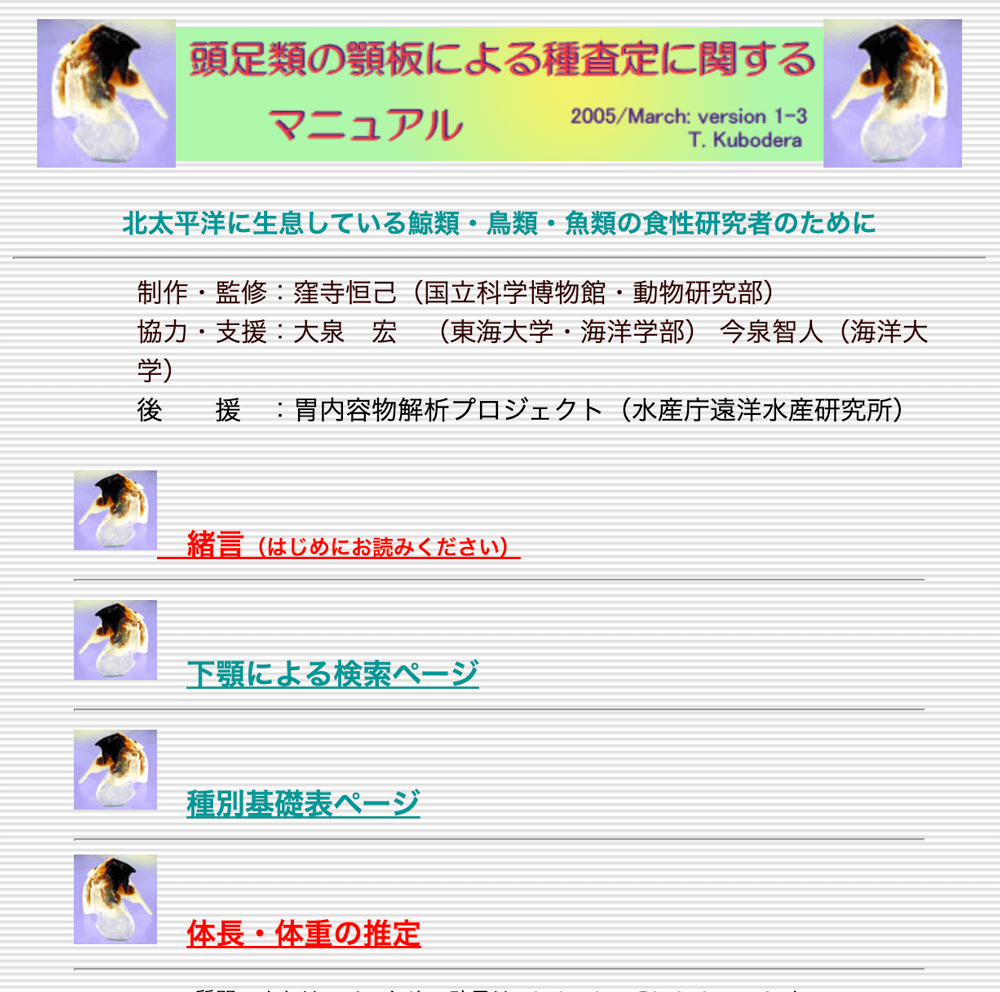中高校生が第一線の研究者を訪問
「これから研究の話をしよう」
第22回
病と形から生物の本質に迫る
海の哺乳類と向き合う熱き研究者
第1章 生物が私たちに教えてくれること
1-1 ストランディングの現場を行く
- 田島
- 皆さん、科博に行ったことがありますか?
- 井上
- ないです。
- 田島
- えーっ、本当? 科博は上野に本館があり、そこで特別展や常設展を開催しています。もし上野に行く機会があったら、ぜひ訪ねてください。今回、皆さんは私の本を読んでくださったとか。2冊とも?
- 井上
- はい。先生は、ストランディングの電話をもらうと、すぐにいろいろなところに行くという生活を繰り返していらっしゃるようですが、疲れたり嫌になったりしませんか。
- 田島
- します、します。「えーっ、今か!」と、だいたい忙しい時に電話がきます。大学院時代は晴れて好きなフィールドに飛び込めたので、毎日がバラ色というか、もう楽しくて楽しくて仕方がなかったですね。憧れの動物たちに出合うチャンスが格段に増え、その動物たちの死因を追究する調査に参加できる喜びでいっぱいでした。その喜びもさることながら、とにかく知らないことだらけだったので、それを吸収するのに精いっぱいな毎日でもありました。
それでも、やはり20年も過ごしていると、年のせいもあるのかな、ちょっと疲れたなあと思うこともあります。 例えばこんな暑い日も私たちは海岸で調査するのですが、怖いのが熱中症で、そのサインが暑いのに鳥肌が立ってくること。そうすると、みんなで十分に休憩したり水分補給しながら、また調査に没頭するというわけです。

2016年1月、阿南市中村海岸に漂着したマッコウクジラ

2024年2月、堺市の堺泉北港に迷い込んだクジラ
- 林
- 最近、ストランディングで一番びっくりしたこと、印象に残ったことは何でしょう?
- 田島
- 毎回びっくりすることばかりですが、最近だと先月、釧路に行ってきました。クジラはあんなに大きな動物だから、私たちの知らない種類なんてないと思いがちですが、私の前任者・山田格(やまだただす)先生はクジラの新種を2種も発見しています。それが2003年と19年で、科博にそのタイプ標本※があります。
19年に論文記載したクロツチクジラが釧路で発見されたので、責務というか、「どうしても行かなくちゃ!」という思いで現地に飛びました。調査の時、特にびっくりしたのが、体長6~7mにしかならないのに、心臓が私の想像を超えて大きかったこと。
- ※タイプ標本:ある生物が新種であることを示した論文内で使われた、その動物の特徴(形質)を保証する標本。

クロツチクジラ イラストレーション 渡邉芳美画
- 田島
- アカボウクジラ科の中で一番大きいのがツチクジラで12m、クロツチクジラはその半分ぐらいのサイズ。18m級のクジラも解剖する私たちにとって、6mはさほど大きくないので、たいしたことはないなと。いつも4時間程度で解剖しているオウギハクジラが5m前後で1mしか違わないので、今回もオウギハクジラほどの大きさを想像していました。
ところが、内臓の大きさが全然違う。相当専門的な話になりますが、1m変わるだけでこんなに心臓が大きくなるのかと驚きました。山田先生がよくおっしゃっていたのが、体長が1m変わると体積は3倍になるということ。そういったことをたまに忘れてしまい、現場で改めて観察すると、びっくりするわけです。そうした想定外の印象もあり、予定通りには全然終わらず、みんなで一生懸命に調査しました。こうしたことは日常茶飯事で、日々、クジラたちに教えてもらっています。

- 林
- ストランディングした個体を解剖する時、ちょっと変な話ですが、何を考えているのですか。
- 田島
- 「解剖できて、うれしいですか」「死体が好きなのですか」とよく聞かれますが、それよりも、なぜ死んでしまったのかと思います。私たちが忙しいということはそれだけ動物が死んでいることになるので、いいことではないのかもしれません。それは消防士さんたちにも当てはまることで、彼らも日頃は万一に備えて訓練などをしていますが、いざ事が起きると真っ先に現場へ急行しますよね。消防士さんたちが忙しくないということは、不測の事態が起こっていないことが多く、それと少し似たところがあります。
生物はいずれ必ず死ぬので、その原因に迫りたい。つまり、人間の病気や死因を追究する学問があるように、動物の世界にもその病気や死因を明らかにする学問があるということです。

ノンコ(手かぎ)で引っ張りながら、クジラ包丁で分厚い皮膚を剝ぐ
- 編集
- 流氷に閉じ込められたシャチがたくさん打ち上がったのは北海道でしたか。
- 田島
- あれは05年ですね。大人のシャチは何とか外に逃げることができたのですが、子シャチが3頭いて、その3頭は流氷に抗えず、どんどん岸に流されてしまい、声を出して大人シャチを呼んでいたそうです。それを聞いて、大人は子どもたちを助けようと戻ってきてしまったので、結局12頭が死んでしまいました。現場にいる人たちはもう見ていられなかったそうです。
海洋に生息し魚のような体つきをしているので、ついつい忘れがちですが、彼らも哺乳類であり、さらに親子の絆も深く、私たちとの共通点も見えてくる。実際、このシャチたちのように、流氷によって海面で息継ぎができないと溺死してしまうのは、私たちと同じですよね。3頭の子シャチは体つきも小さく、体の色がクリーム色で、実際、胃の中からは母乳が観察されたので、乳飲み子だと分かりました。

北海道羅臼町で流氷に閉じ込められたシャチ
1-2 解剖するのは何のため?
- 編集
- ご著書によると、解剖学を専攻する研究者が少なくなってきたとか。
- 田島
- そうですね、残念ながら激減しています。解剖学を含む基礎学問は大昔から進められてきた歴史もあり、今ではやり尽くされた印象を持たれがちです。それでも私たちが日々行っている調査・研究からは、毎回とはいきませんが、新しい発見や知見が得られています。そうした膨大な、いい意味での「無駄な時間」の中に実は重要で大切なお宝が眠っている、本当の心の豊さが潜んでいると感じます。

- 井上
- 先生は解剖学のどこに面白さを感じたのでしょう?
- 田島
- 私は、獣医大時代、いろいろなことを学ばせてもらいましたが、その全てが今につながっていると言っても過言ではありません。例えば、私は病気を専門とした研究室で学生時代を過ごしていましたが、病気というのは生物の正常状態が破綻すると起こるわけです。とすると、生物の正常とはどういうことなのかを知る必要が生じます。そうすると、いろいろな生物や動物の正常を知ることにも興味が湧いてきて、教科書のどのページをめくっても必要な情報ばかりになります。
例えば、腎臓が尿を作ることは多くの人が知っていると思いますが、実際、顕微鏡で腎臓の組織を観察すると、尿を作る細胞たちがいて、その細胞たちが異常をきたすと、変な言い方ですが、ちゃんと病気になってしまいます。改めてその病気の部分を顕微鏡で観察すると異常が発見できるし、新たな発見もあります。このような仕組みや経過を自分の目で確認できることに面白みや奥深さを感じ、病理学を専攻するようになりました。
解剖学も同じで、自分たちを含めた脊椎動物や哺乳類を解剖学的に比較・検証することは単純な作業のように見えますが、その過程で新発見や新知見を得られるかは、実は私たち自身の能力にかかっていることを痛感させられます。そういうところに面白さを感じてしまうんですね。
- 井上
- 解剖を見学することってできるんですか?
- 田島
- 調査は、個体が発見された海岸で行ったり、各大学で研究者が一堂に会して実施します。海岸での調査にたまたま出くわした方が見学されることは多々ありますね。大学での調査も、事前に何らかのコンタクトがあれば、見学できる機会があるかもしれません。
- 林
- 結構、力がいると思うのですが。
- 田島
- ははは、そうですね。相手は体長18mから2mまでいろいろですが、得てして体力勝負なところはあります。私は中・高校時代、バスケットボールに明け暮れていて、幸いにも体力には自信があったので、よかったです。
1-3 動物の繁殖戦略を知る ~著書『クジラの歌を聴け』を読んで~
- 田島
- ところで、2冊目の本はどう思いましたか。意味は分かりましたか?
- 井上
- ちょっと難しかったです。
- 田島
- そう、2冊目は少し専門的すぎましたね。
- 林
- でも、表紙がすごくかわいい。
- 田島
- 2冊とも有名な装丁家に担当していただき、非常にポップな表紙になりました。
- 井上
- 学校で空き時間に読んでいたら、隣の席の子が自分も読んだと。その子といろいろ話せて、すごく楽しかったです。
- 田島
- うれしいですね。本でも触れているように、獣医でいると性や繁殖はとても重要な内容で、それは人間も同じ。ヒトも生物として捉えるならば、生物は、実はとても単純な自然の摂理の中で自らの営みをまっとうしています。ヒトは大きな大きな頭で少し考えすぎてしまうところがあり、自分が生物であることすら忘れてしまう場合がある。それは、ヒトという生物にとってはよくないことが多く、そうした時は、周りにいるたくさんの生物や動物からいろいろ学べることがあるんじゃないかなあ、と思っています。実際、私も家にいる愛猫たちから毎日多くのことを教えてもらっています。
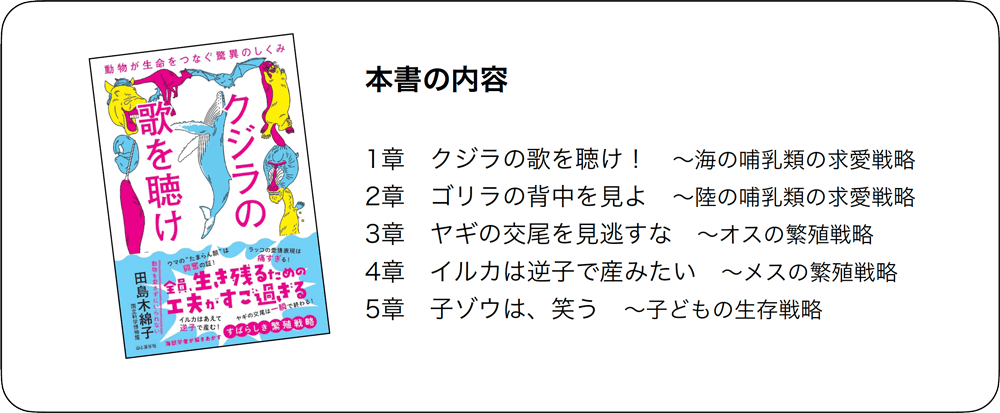
- 井上
- この本を読んで、女子というか、メスが堂々としていて、こびているのはオスの方だから、ヒトもそうなればいいなとちょっと思ってしまいました。

- 田島
- そうですね。でも、実はメスもすごく真剣で、強いオスの遺伝子を残すという使命感でオスを選んでいる。強いオスの遺伝子があれば、その種が未来永劫に繁栄する可能性が高くなるので、オスもメスもそれはそれは必死で、そこには明瞭な理由があるんですね。ヒトの場合はもう少し複雑で、大きな大きな頭で、この場合も考え過ぎてしまうところがある。そうした時には、繰り返しになるけれど、周りの動物たちのみっともないぐらい真剣でひたむきな生き方を見習うことができるんじゃないかなあ、と感じています。
1-4 イカのビークで種同定
- 田島
- 頭足類の何が好きなの?
- 林
- 例えばタコは足の先に脳が全部あるみたいな、すごく賢い気がして。

- 田島
- 賢い? たぶん、神経終末が足先にあるということですね。そこで、また1つ考えてほしいのが「賢いとは何か」ということ。人間でいうと、脳でたくさんものを覚えられる、記憶できる、計算が速いということで賢さを表すことがあるけれど、生物の賢さはまたちょっと違う場合がある。彼らはいかに要領よく生きるかが最も重要。人間の世界でいうと「そんなやり方はずるいよ」「楽しちゃ駄目だよ」となるかもしれないことでも、要領よくて、ずる賢いぐらいがちょうどいい場合もあるんですね。タコも、足先に神経終末があることが、彼らの生き方に有利に働く賢さなのかもしれない。そういう視点から、なぜそこに神経終末を作ったのかをもう少し深掘りしてみるのもいいのかもしれないですね。
- 林
- はい。
- 田島
- 名誉研究員である窪寺恒己(くぼでらつねみ)先生は頭足類研究の第一人者のお一人ですが、窪寺先生たちが科博のホームページに頭足類の種同定ができるページを作成されました。例えばマッコウクジラがイカを食べると、イカのビーク(Beak)、つまり上下の顎板(がくばん)※が消化されずに残っていて、それで種同定ができる。ソデイカやドスイカ、カムチャッカテカギイカなどいろいろいるけれど、そのビークが整理されています。もしよかったら、一度のぞいてみてください。
- 林
- ぜひ拝見させていただきます。
- ※顎板:カラストンビあるいはトンビとも呼ばれる。