人類が繁栄した理由は何かという根源的な問い
———京都大学での思い出を教えてください。
サークルや部活に所属するというようなタイプではなく、大学時代は必死に勉強していました。興味に沿って履修科目を選択するのですが、生物とか脳に興味があって、細胞接着物質の発見者として知られる竹市雅俊先生の研究室に所属しました。竹市先生は2002年3月に京大を退官されて、神戸の理研CDB(発生再生科学総合研究センター、現在の生命機能科学研究センター[BDR]の前身)に移られたので、ラボのメンバーもそのまま理研に引っ越して、大学院時代はずっとCDBで過ごしました。

2002年、竹市先生を囲むラボメンバーと(前列左から2人目)。竹市先生は前列中央
———そこではどんな研究を?
当初から神経に興味があったので、そういう研究をやっていました。当時は遺伝子全盛で、ある遺伝子をノックアウトしてその遺伝子が何に効いているかを調べるといった分子生物学が主流でした。ぼくもそういう研究をしていましたが、それに嫌気が差したというか、もっと遺伝子で記載できないような生命現象の研究がしたいと思うようになったのです。
———遺伝子で記載できないような生命現象というと?
これは、研究を始めた当初から抱いていて今も変わらない命題ですが、ヒトがなぜほかの動物と違う能力を獲得し、このように繁栄しているのかを明らかにしたいというのがぼくの根源的な問いで、それに大きく寄与しているのが言葉の力だと思うのです。言葉によって同世代でのコミュニケーションだけでなく、世代を超えて情報を蓄積することができるようになった。ここでキーになるのは、遺伝子が全部を決めているのではなく、生後の育ち方とか、言語コミュニケーションなど、経験的に脳が変わっていくということが大事なのではないかということです。
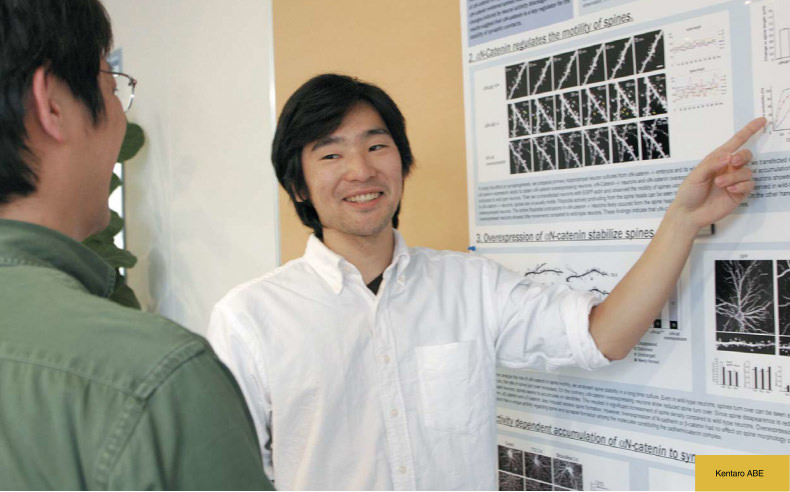
修士時代のポスター発表。2004年
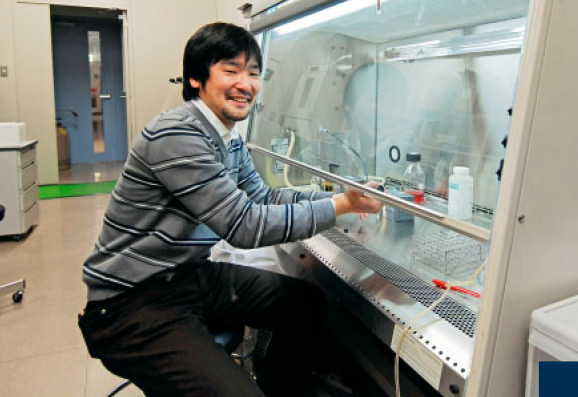
ラボで実験。博士課程2007年
———それを探究するには遺伝子の研究だけではダメだというわけですね?
脳の高次機能とか言葉というのは、1つの遺伝子でどうこうなるようなものではありませんからね。では、そうした後天的な能力をつくっていく神経メカニズムの研究はどこまで進んでいるかというと、経験依存的に脳がどう変わるのかを分子レベルで明らかにするためにヒトそのものを対象に実験を行うのはなかなか難しいし、かといって適切なモデル動物もいないため、あまり研究は進んでいませんでした。
ところが、2005年ごろから光遺伝学などいろいろなツールが出てきて、それまでは脳は複雑すぎて手が出せない領域だったんですが、次第にいろいろなアプローチができるようになってきた。そこで、小鳥の研究に飛び込んだわけです。
———先生が小鳥の研究を始めようと思ったとき、日本で鳥の研究はどの程度進んでいたんでしょうか?
古くはカリフォルニア工科大学の教授だった小西正一先生が知られていますね。当時は、岡ノ谷一夫先生などが研究を進めておられましたが、日本より海外のほうが活発に研究を展開していて、神経科学の一分野として小鳥のさえずりの神経機構の解明などに取り組む先生がたくさんいました。カナリアのさえずりから成鳥の脳で神経新生があることを発見したロックフェラー大学のフェルナンド・ノッテボーム博士やマサチューセッツ工科大学のマイケル・S・フィー博士といった超一流の神経科学者が、最新の技術を使って、画期的な論文を次々に発表していました。
———すると海外に行って研究しようと?
当初は博士号を取ったあとは留学しようと考えていたのですが、たまたま、アメリカ留学中に鳥の研究をして、帰国後に大阪バイオサイエンス研究所のシステムズ生物学部門副部長をされていた渡邉大先生が京大の生命科学研究科教授となり、小鳥を使った研究を始めるというので話をうかがいに行きました。渡邉先生と話すうちに、留学して大御所の先生のもとで研究をするのもいいけれど、どうせならゼロから自分たちで立ち上げるのも楽しいかなと思い、渡邉先生の研究室の助教となり、一緒に小鳥の研究をすることにしたのです。
———渡邉先生はどんな先生でしたか?
おおらかな先生で、短いスパンで成果を出すことよりも、生物学や神経科学にとって真に大切なことをずっと追究していくというタイプの先生で、多くの学びがありました。

渡邉研究室での助教時代(前列左から2人目)。後列左から5人目が渡邉先生