腎臓病を悪化させるタンパク質を発見
———そこから本格的な研究生活のスタートですね。
学部生のときに私を目覚めさせてくれた土井俊夫先生のもとで研究を始めましたが、大学院の1年目にもらったプロジェクトがあまりうまくいかず、「先生うまくいきません」の連続でした。そうこうしているうちに土井先生が徳島大学の教授にご栄転されることが決まりました。
———どうしましたか?
私は京都に残ったのですが、自分のいたグループがなくなってしまったのでブラブラしていたら、当時の教授の北徹先生が「お前、何をしてるんだ。研究費をやるから自分でプロジェクトを考えなさい」と声をかけてくださいました。まだ大学院の2年目で、論文を読んでもやったことのない実験ばかりでイメージがわかず、ウンウン悩み、プロジェクトの産みの苦しみを味わいました。横にはちゃんとボスからテーマを与えてもらっている大学院生もいて、「いいなぁ、うらやましいなー」と思いながら、テーマ探しを続けました。
———そこで選んだテーマは?
当時、教室内に「実験医学」とか「細胞工学」といった雑誌が山と積んであって、むさぼり読むうち、中野さんという当時、塩野義製薬で研究されていた人が見つけたGas6というタンパク質の話が載っていました。これがビタミンKの存在下で活性化し、平滑筋細胞を増殖させる働きがあると書かれていて興味を持ちました。
———Gas6と腎臓病とは何か関係があるのですか?
腎臓は、細い毛細血管が毛糸の玉のように丸まった「糸球体」で血液中の老廃物や塩分をろ過して、尿として身体の外に排出しています。末期の腎不全の大半は、この糸球体が炎症やなんらかの障害を起こす糸球体疾患によるもので、博士課程でその原因を探っていました。
毛細血管を内側からつなぎ合わせて糸球体の生理機能を担っているメサンギウム細胞の増殖が糸球体疾患の発症に関わっていると考えられており、治療薬として血液凝固を阻害するワーファリンという薬が使われていましたが、なぜ効果があるかはわかっていなかったのです。
ワーファリンはビタミンKの働きを抑えることで血液凝固を阻害します。一方で、Gas6というタンパク質はビタミンK依存性の増殖因子として働いている。そして平滑筋細胞とメサンギウム細胞はよく似ているのです。だからGas6こそがメサンギウム細胞を増殖させていて、それを阻害しているのがワーファリンなのではないかという仮説を立てました。
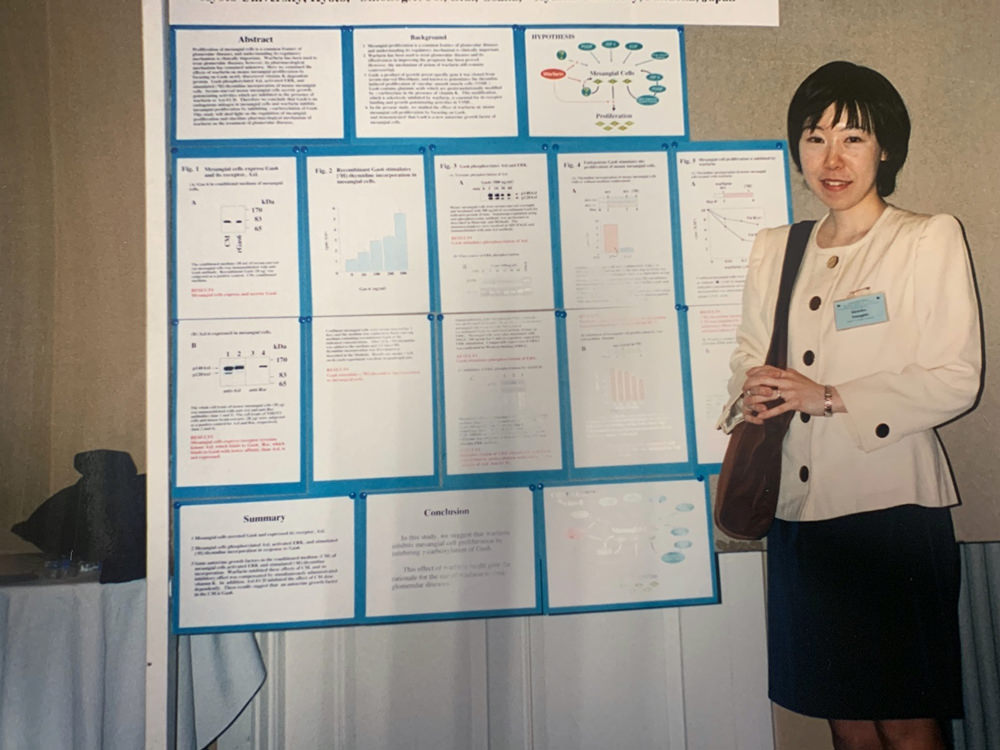
大学院時代のKeystone symposia(アメリカ・コロラド州キーストーンで行われる国際学会)での発表。初渡米、初めての英語での発表だった。
———なるほど。
北先生の名前で中野さんに手紙を書いて、タンパクや抗体など、いろいろなマテリアルをいただいて、実験手技は、当時動脈硬化ラボにおられた先生方に教えてもらいました。仮説を裏付ける研究を進め、糸球体疾患を悪化させる一連の仕組みを4本の論文にまとめることができ、それで学位をいただきました。
———博士号を取得して、次のステップは?
大学内で合同発表会があって、「Gas6でこんな発見がありました」と発表したところ、当時、薬理の教授だった中西重忠先生からこう言われたのです。「今、君の目の前にある、自分でできる研究をするのは必要なことだ。しかし、今の自分ができないようなことも考えているかどうかが、研究者として一流かどうかなんだ」と。それを聞いて、このままじゃだめだ、一皮むける必要があると思い、留学を考えました。
———留学先はどこにしましたか?
腎臓の超一流のラボを探しましたが、どれも北先生から「おまえは一生腎臓をやるんだから、腎臓のラボには行くな」と却下されてしまうのです。そのときは「なぜ?」と思いましたが、今にして思うと北先生のおっしゃる通りで、腎臓のラボに行ったら、その先生のスタイルが自分の研究スタイルになってしまうと思われたんでしょうね。結局、アメリカのハーバード大学で細胞の運命決定の研究を行っている先生のところに留学が決まり、やれやれよかった、あとはビザをとるだけ、となったとき、その先生が急死してしまったのです。
———ということは留学も中止ですか?
すごいショックでした。日本での仕事をすべてクローズして留学の手筈を整えていたので、留学が中止になるともう居場所がないんです。困ったなと思って、いろいろ探していたら、北先生から「柳沢正史先生のところへ行ったらどうか」と言われました。
———筑波大学で睡眠のご研究を率いている柳沢正史先生ですか?
はい。柳沢先生は睡眠覚醒を制御する神経伝達物質の「オレキシン」や、血管を強力に収縮する作用がある「エンドセリン」を発見した方です。当時柳沢先生はテキサス大学の教授に就任されてアメリカにいらしたのですが、2001年に科学技術振興機構(JST)の「戦略的創造研究推進事業・総括実施型研究(ERATO)」に採択され、「柳沢オーファン受容体プロジェクト」の統括責任者として新規プロジェクトをスタートするため、研究員を募集中だったのです。一時日本に帰って来られるというので、「会ってみたらどうや」と北先生にアドバイスされました。
———お会いになってどうでしたか?
お会いしてみて、「この人は天才だ」と思いました。医学では、人体を解剖学、組織学、病理学、生理学、薬理学、臨床医学といういろいろなレイヤー(階層)で繰り返し学ぶのですが、柳沢先生の頭の中はそのレイヤーがきっちりと積み重なっていて、何か未知の現象を見つけたときも、その重層化された知識をもとに、縦横無尽な切り口で解き明かすことができるのです。
そこで、腎臓は一切封印して、柳沢先生のもとで一度勉強してみようと思いました。
———ポスドク先は、テキサスではなく日本だったのですか?
最初はテキサス大学に行くつもりだったのですが、「日本でERATOのラボをスタートさせるから、君、立ち上げに参加してみたら」ということで、グループリーダーの先生方のもとで、ラボの立ち上げに関わらせていただいたことは貴重な経験になりました。
グループリーダーの先生方も素晴らしく、世界のトップレベルのサイエンティストのご指導のもとで研究ができました。2年半の間、未知の生理活性ペプチドを探索するプロジェクトに取り組み、USAG-1という分子を見つけたちょうどそのとき、京大で21世紀COE事業がスタートすることになり、助教授として迎えてくださるという話が来たので、京大に帰ることにしたのです。
———PI(研究室主宰者)として研究を進めることになったのですね。どんな研究に取り組んだのですか?
見つけたばかりのUSAG-1についての研究ですね。USAG-1は腎臓に特異的に発現し、腎臓病を悪化させるタンパク質として新たに見つけたものですが、同じような働きをするGas6と違うところは、USAG-1はGas6よりももう少し病状が進行してから大事になってくる分子だということです。Gas6が腎臓病の初期に働くのに対して、USAG-1はより後期まで働くことから、USAG-1の働きを抑える新薬を開発できれば、腎臓機能の悪化を抑えられるのではないかと意欲的に取り組んでいたのですが、やがて研究に転機が訪れるのです。