ヘッセの『車輪の下』を読んでショックを受けた中1のころ
———先生はずっと大阪ですね。
大阪・心斎橋の近くで生まれ、育ちました。実家が商売をしていて、商業ビルの4階が自宅兼事務所でいつも人が大勢出入りして、家なのか会社なのかわからないようなところで暮らしていましたね。まわりに自然なんか全然なく、近くの公園で土を掘るとコンクリートが出てくる、そんな環境。小学校も繁華街から5分ぐらいのところにありました。

幼いころ
———昔でいったら“船場(せんば)のぼんぼん*”、東京でいうと銀座で育った感じですね。どんな子供だったのですか?
書斎にいろいろな図鑑が置いてあって、小さいころはそれをよく見ていました。小学校に入ると、図鑑に載っている昆虫を集めたり、鉱物標本を集めたりと収集癖が出てきて、凝り出すと止まらない。一番お金がかかったのは切手収集ですね。シリーズを完成させるために、高い切手を親に頼み込んで買ってもらったことも…。
*船場のぼんぼん:金融・商社・薬・繊維の問屋や商店が軒を連ね、商都・大阪の中心地として栄えた船場の裕福な商家の跡取り息子

小学生、おそらく低学年のころ
———とにかく集めてコンプリートするのが好きだったんですね。
駅の名前を覚えたりもしました。東海道本線の駅名を全部覚えるとか。ファミコンとかゲームなどはあまり興味がなく、それよりはものを集めたり、何かを全部記憶したり、そういうのが好きなちょっと変わった子。親は「この子は天才肌かな」と思ったらしくて、中学は中高一貫の進学校に入りました。
———どんな学校生活でしたか?
読書が好きで、ジャンルにこだわらず手あたり次第読んでいました。バスケットボール部に入ってスポーツもちょっとやったんですが、文化部にも入って“BASIC”言語を使ってコンピュータのプログラミングもやりました。
———得意科目は?
そのころ好きだったのは理科です。本を読むのは好きだったけど国語は好きじゃなかった。作者の意図を読み取れとか、本の解釈を強要されるのがイヤで、本は自分の感性で読むものであって国語に正解があるのはおかしいと思っていましたから。
———そのころ読んだ本で印象に残っているものはありますか?
思春期でもあったので、ヘッセの『車輪の下』を読んでショックでした。小さな町で神童と呼ばれ将来を嘱望された主人公ハンスが、エリート養成校である神学校に入学するけれどもプレッシャーに押しつぶされて結局は死んでしまう話です。中学1年のときに読んで、ハンスを自分と重ねてけっこう落ち込みました。ぼく自身、小学校時代は「いろんなことを知っていて賢い子」と言われたけれど、進学校に行ったらもっとすごい子がいっぱいいてたいしたことない(笑)。中学校に行ってだいぶ考えが変わりましたね。
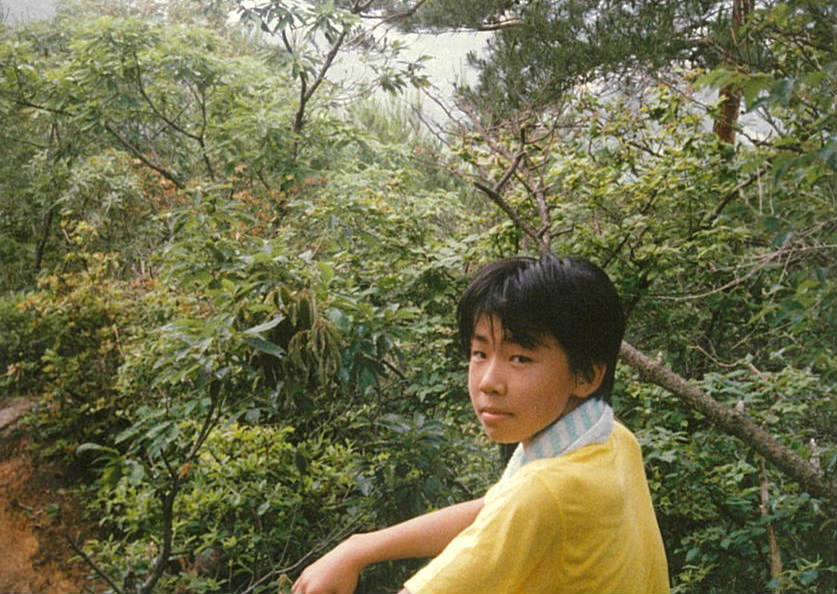
中学時代
———高校生になってからは?
中学時代は部活をやりながらでしたが、高1からは学校自体が受験勉強一本という感じ。当時は第2次ベビーブームの真っ只中で、受験戦争がけっこう激しかったですからね。
———勉強はどうでしたか?
物理がメチャメチャ楽しくて、教科書では物足りなくなるほどでした。そこで大学生向けの本を買ってきて勉強したりしました。物理の試験問題って、大学で習う法則をわかりやすくしたような問題が多いんですよ。すると、出題の背景がわかって一段上になった気分で問題が解けて、勉強が楽しくなるんです。
英語も好きでしたし、数学もそんなに嫌いじゃなかったから、受験勉強も楽しかった。あと、社会で選択した世界史も、さまざまな民族の歴史や対立、同盟関係などを知るうちにどんどんおもしろくなって、大学に行ったら絶対海外に行こうと思うようになりました。
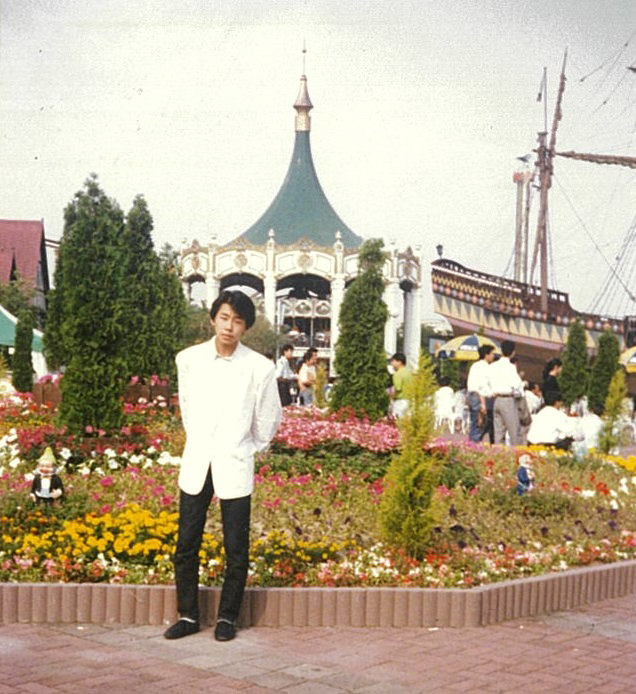
高校時代
———医学部を志望した理由は?
医学への興味は漠然とありましたが、それより好きだったのが物理で、理学や工学系も選択肢のひとつでした。それなのになぜ医学部を志望したのかというと、自分が将来、その学問にどれだけ貢献できるかを考えたとき、物理ではたぶん無理なんじゃないかと思ったのが大きいですね。
———物理が好きというだけではダメなんですか?
物理にはいろいろと人の名前のついた法則がありますが、一人の大天才があらわれて、それによって100年ぐらい歴史を一挙に進めていく。数学も同じことがいえて、学問の中ではデカルトがまだ生きているわけです。物理はアインシュタインとかボーアとかシュレディンガーとか、本当にすごい大天才が進めるものであって、彼らの業績を勉強して楽しむことはできるけれど自分はとても太刀打ちできない。その点では、生命科学ならみんなが貢献するチャンスを持ちうる気がして、医学部を志望することにしました。もちろん医師になって人を助けたいという気持ちもありましたが、ゆくゆくは医学研究をしようと考えたのです。