大学院はカリフォルニア、ポスドクはスイスへ
———大学院はカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)ですね。選んだ理由は何ですか?
引き続き神経細胞と運動機能について調べたいと考えていたところ、UCLAで脊髄の運動回路を研究している先生がいると聞いたんです。運動系の回復の研究をしているレジー・エジャートン(Reggie Edgerton)先生と、軸索(神経細胞の長い突起部分)の再生を研究しているパトリシア・フェルプス(Patricia Phelps)先生が共同研究をなさっていました。そこで、研究室に入れていただき、脊髄損傷の後に軸索の再生を促すことで歩行機能がどのように回復するかを研究したのです。2人の良い先生に恵まれ、研究だけでなく論文の書き方をはじめ研究者としての基本も学び、非常に良い経験になりました。
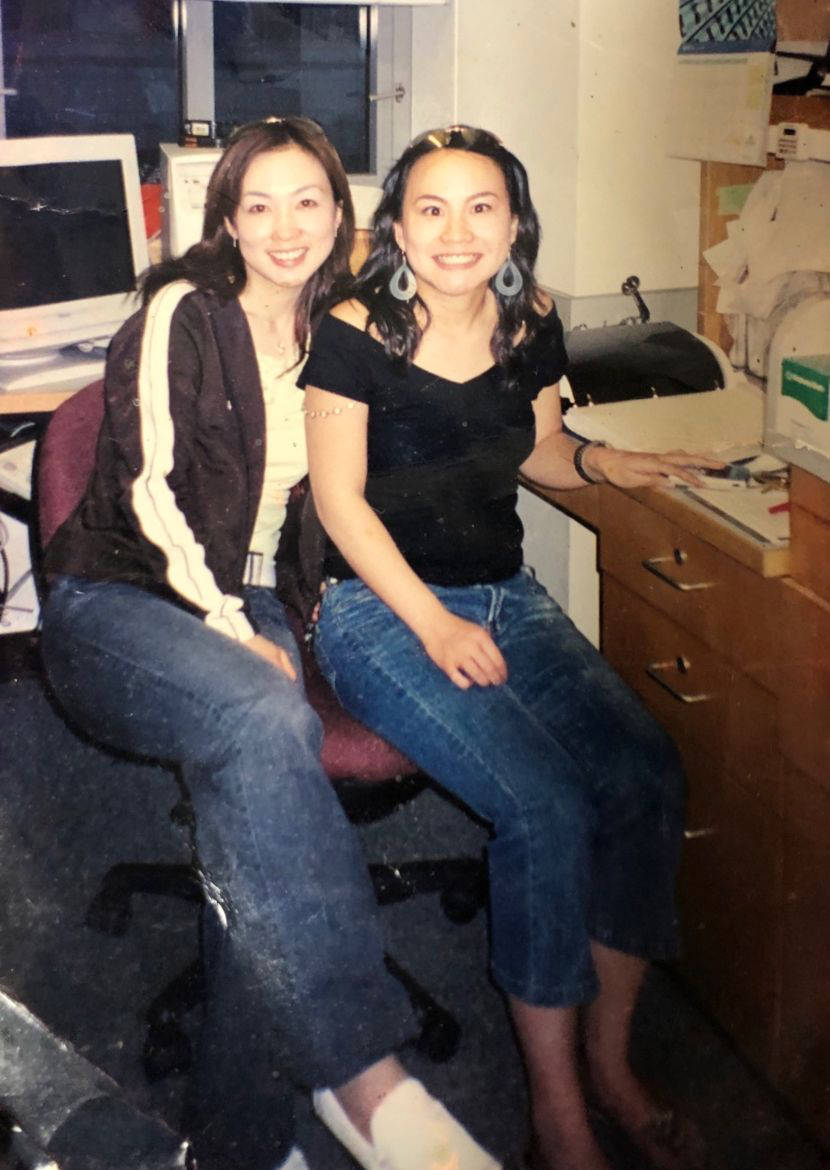
研究室にて。姉(左)が遊びに来た時のもの
———神経細胞と運動機能の回復の研究を深めていったのですね。
さらに研究を進めるうち、運動機能が回復するときに脊髄の神経細胞がどのように変化するかを調べてみたくなりました。そのころ、同じ研究室からスイスに移った先輩に相談をしたら、バーゼル大学のシルビア・アーバー(Silvia Arber)先生を紹介してくれたんです。ちょうどシルビア先生は行動解析ができる人を探していたところで、それは私が大学院でやっていたこと。じつは、私は遺伝子の組み換えの実験手法も学びたかったんです。それができれば、神経細胞の活動によって行動がどう変わるかを実験できるようになります。シルビア先生がその技術に強いということが彼女の研究室を選んだ理由のひとつでした。
———シルビア先生の研究室で、具体的にはどんなことを研究したのですか?
自分の身体の位置や動き、力の入れ具合など、自分の内部を感じる感覚のことを「固有感覚」といいます。たとえば歩いたり、階段を上ったり降りたりする際に、筋肉や関節の動きが脳に送られ、自分の身体がどのように動いているかを適切に判断することができるようになります。こうした固有感覚が運動機能の回復や運動制御にどう関わっているのか?という課題で研究を進めました。
脊髄は固有感覚の信号が最初に入ってくるところで、そこで信号を情報処理して脳へ送ります。その過程で中枢神経の細胞がどのように変化していくのかを解析しました。
まず、固有感覚神経がないマウスを使い、脊髄を一部損傷した後の歩行の回復を見ていきました。正常なマウスは、軽/中度の損傷の場合は、自然に歩行機能がある程度回復するのですが、この固有感覚神経がないマウスだとまったく回復が見られないんです。これは普通に起こるはずの、軸索が伸びることによる神経回路の再編が起こらないためだとわかりました。脊髄の固有感覚神経がないと信号が脳に届かないので、軸索を伸ばす指令も出ない、と考えられます。この結果は研究室に入って4年目に論文にしました。

バーゼル時代は毎週末のようにスイスアルプスでスノボー、スキーを満喫。

学会で研究発表した日の夜

インターラーケン(スイス中央部高地)でのキャンプ(右から3人目)
———研究者として自立を考えたのは、いつごろですか。
自分の研究室を持ちたいと思ったのは、ポスドク(博士研究員)になって3年ぐらいしてからです。
じつのところ、スイスに行ってみたら想像以上に研究室のレベルが高くて、ついていけるようにいつも必死でした。シルビア先生は2022年にThe Brain Prizeという神経科学界ではもっとも名誉な賞を受賞されています。そんな先生の研究室ですから、期待されることもプレッシャーも大きいんです。でも、だからこそ楽しいというか、研究のモチベーションになってきたんですね。先生はかなり自由に研究をやらせてくれる方でしたが、自分で研究室を主宰し、独自の道を切り拓いてみたいという気持ちが徐々に強くなっていきました。