不眠不休で競り勝った遺伝子レース
———修士を出て、企業の研究所に就職したのはなぜですか?
当時はバブルがはじけた直後で就職氷河期に突入し、消去法で博士課程に進む人も多かった。それよりは頑張って企業に入ったほうが、大きな研究ができるのではと考えたのです。大都市より地方が性に合っていると考え、栃木の杏林製薬の研究所に入りました。基礎研究もできるし、自然もあり好きなバイクで通勤できる理想の環境だったんです。入ってみたら同僚もいい人たちばかりで、おまけにソフトボールも強かった。さっそく入部して週末は練習と試合に明け暮れました。
———研究所ではどんな研究に取り組んだのですか?
薬効のメカニズムを明らかにする部署で、アルツハイマー病の原因遺伝子について研究していました。アルツハイマーは神経細胞の細胞死ですから個人的にも興味があったし、分子生物学のプロフェッショナルの先輩方に鍛えられてかなり研究力がついた。でも、そのころから細胞死の研究が一気に進み、世界中で次々に発表される研究成果に圧倒され、自分もその最先端に行きたいという気持ちが強くなりました。
———それで、大学の博士課程に戻るのですね。
細胞死に取り組む研究室を調べて、当時大阪大学で助教授をされていた三浦正幸(みうら・まさゆき)先生の研究チームに入れていただきました。阪大には同じく世界の細胞死研究を牽引していた長田重一先生や辻本賀英(つじもと・よしひで)先生もいらっしゃいましたが、三浦先生は私と年も近く、興味のある論文の話で盛り上がって「一緒にやりましょう」と言ってくださったんです。
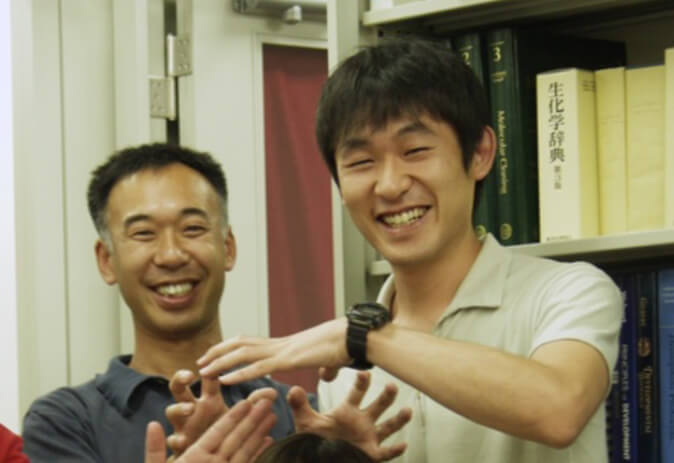
博士課程時代。左が三浦正幸先生。
———三浦先生のチームでやることは決まっていたんですか?
最初に与えられたのは、辻本先生が発見した細胞死を抑制するがん遺伝子のひとつ「Bcl-2」をショウジョウバエから探し出すことでした。ハエのBcl-2遺伝子はまだわかっていなかったんです。オーストラリアの研究者も同じ遺伝子を解析しているという情報が入り、毎日、朝10時から夜中の3時まで、休日も返上してラボに通って実験しました。
———どちらが先に発見するかの競走ですね! その結果は?
負けるわけにはいかないので必死で実験し、研究をスタートして半年で論文を投稿しました。結局、オーストラリアのグループは私たちの1か月後、追ってアメリカの2つのグループも論文を発表し、結果的に4つのグループのレースだったとわかりました。
その後、自分でBcl-2の働きを促進したり抑制したりする遺伝子を探してみようと、5000系統もの変異体のスクリーニングを続けました。そしてBcl-2とは関係なく、単独で細胞死を起こす遺伝子を見つけたのです。
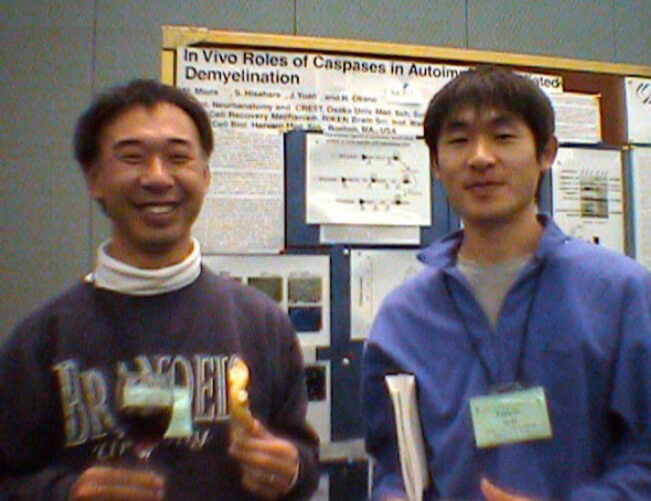
三浦先生とともにアメリカの学会(キーストーンシンポジウム)に参加。初めて英語で口頭発表。
———発見したのはどんな遺伝子ですか?
細胞死を引き起こす代表的な遺伝子の一つ、「TNF(tumor necrosis factor;腫瘍壊死因子)」です。TNFはそれまで哺乳類が進化によって獲得したと考えられていた遺伝子で、無脊椎動物で確認されたのはこれが初めてでした。好きな山の名にちなんで「Eiger(アイガー)」と命名しました。私は修士課程のころから登山を始め、論文投稿した後はテントを背負って一週間ほど日本アルプスを縦走するのがお決まりでした。アイガーはトレッキングしただけですが、その美しい姿に感動して、いつか重要な遺伝子を見つけたら名前に付けようと決めていたんです。

修士時代から始めた登山。北アルプスにて。
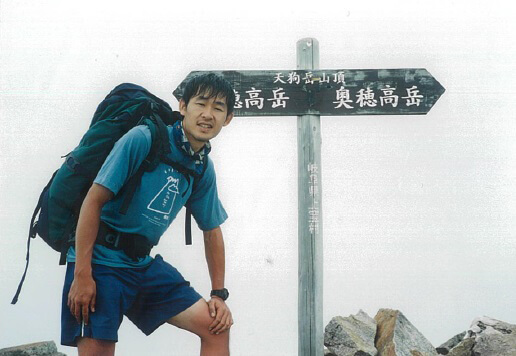
北アルプス天狗岳山頂にて。
———好きな山の名前を遺伝子に付けたんですね!
その後、Eigerとともに働くパートナー遺伝子として、後輩が見つけた受容体遺伝子には「ヴェンゲン」、フランスの研究グループが発見した受容体遺伝子には「グリンデルヴァルト」と、いずれもアイガーの麓にある村の名前が付けられたんですよ。
さらに研究を進めると、Eigerによる細胞死は、哺乳類から線虫まで細胞死に共通して関わっている酵素「カスパーゼ」ではなく、「JNK」という別のシグナルによって引き起こされることもわかり、2002年に論文で報告しました。
しかし、腫瘍化するだろうと思ってEigerをノックアウト(Eiger遺伝子がない状態に)しても、そのハエは野生型と変わることなくピンピンしていたんです。Eigerには何か重要な役割があるに違いないと信じてはいましたが、その答えはすぐにはわかりませんでした。