中高校生が第一線の研究者を訪問
「これから研究の話をしよう」
第13回
昆虫から死後経過時間を推定!? 知られざる法昆虫学の世界
第3章 研究にまつわるエピソード
●研究への心構え
- 佐藤
(鈴) - 研究に対する考え方について質問です。本に「死体やウジの話をすると周りに距離を置かれる」と書いてありました。しかし、その後、「どうせわかってもらえない」のではなく、「法昆虫学が不要な社会になればいい」と書かれているのを見て、そういう考え方もあるのだなと感心しました。私のやっている天文学も、拒絶ではないのですが、「ロマンがあるね」「夢があるね」で終わってしまい、深掘りをされないことがあります。先生も最初、距離を置かれて傷ついたと思うのですが、そこから「自分の研究が不要な社会になってもいい」という考え方に変換できたのはどうしてですか。
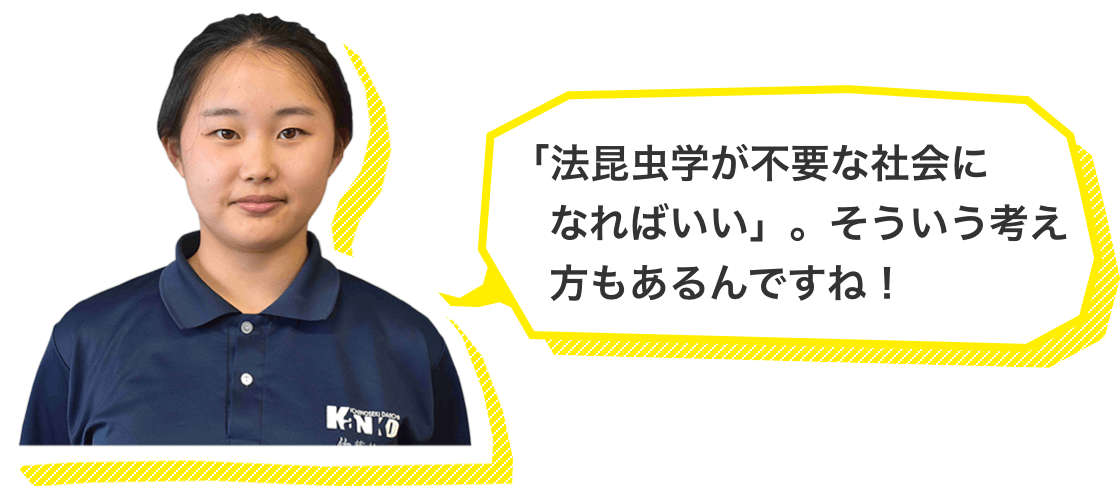
佐藤鈴音(さとう・すずね)さん(高校2年生)
- 三枝
- うーん、それはなかなか難しい質問ですね。やはり分野の特性というか、「法昆虫学はそれほどメジャーでなくてもいい。有用性がわかる人だけでいい」というところもあると思います。でも最近、学会で、男性には「わあー、気持ち悪い」「おまえ、何やってるんだ」と拒絶されるのですが、不思議なことに女性研究者には声をかけられます。
- 佐藤
(鈴) - えーっ(笑)。
- 三枝
- 私の分野に関しては女性のほうが興味があるのか、結構、多くの女性研究者に声をかけれらます。この間も、これは死体に絡まないのですが、本学の卒業生で研修医をやっている人がいて、研修先で「傷口にウジ」ということが出たそうです。即座に私のことを思い出し、連絡をくれました。それも、女性医師です。
最初は仲間がいない状況があるのかもしれないけれど、同じようなことに興味を持っている人は必ずいます。絶対に会えるというか、周辺分野にも興味を持って付き合いを広げていくと、いずれは本当にぴたっと興味が合う人にたどり着くことがあると思います。
- 佐藤
(鈴) - ありがとうございます。頑張ります。
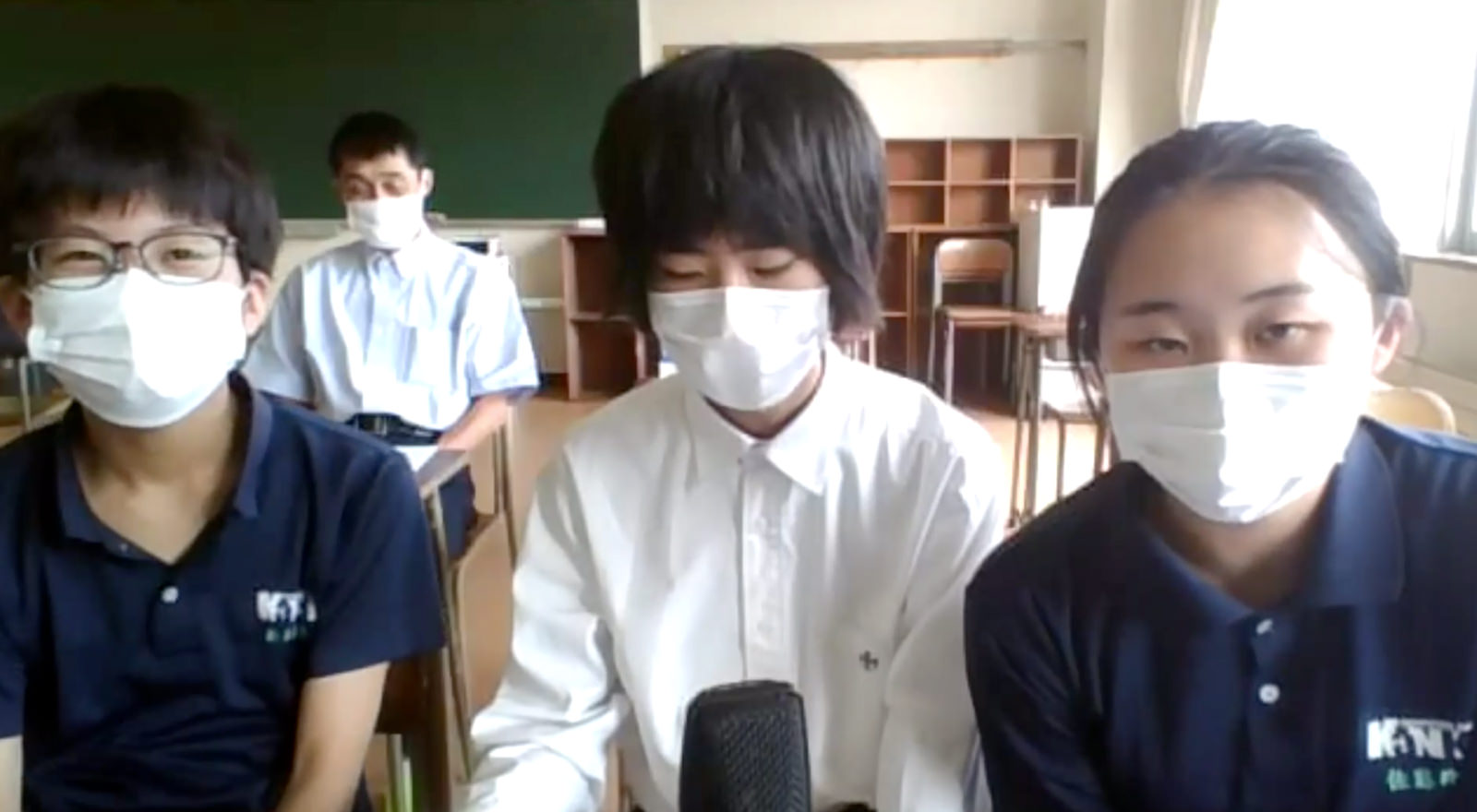
●法昆虫学への関心度
- 鈴木
- 先生から見て、日本における法昆虫学に対する関心度はどのくらいですか。
- 三枝
- ここ数年、年に何件か他県の警察から依頼が舞い込んでいるので、少しずつ認知度も高まってきているようです。学会に行くと、これまでは本当に隅っこにいるマイノリティーだったのですが、いまは「三枝先生ですか」と声をかけられるようになってきました。
- 鈴木
- すごーい。先生の他に、法昆虫学者って日本には何人ぐらいいるのでしょう。
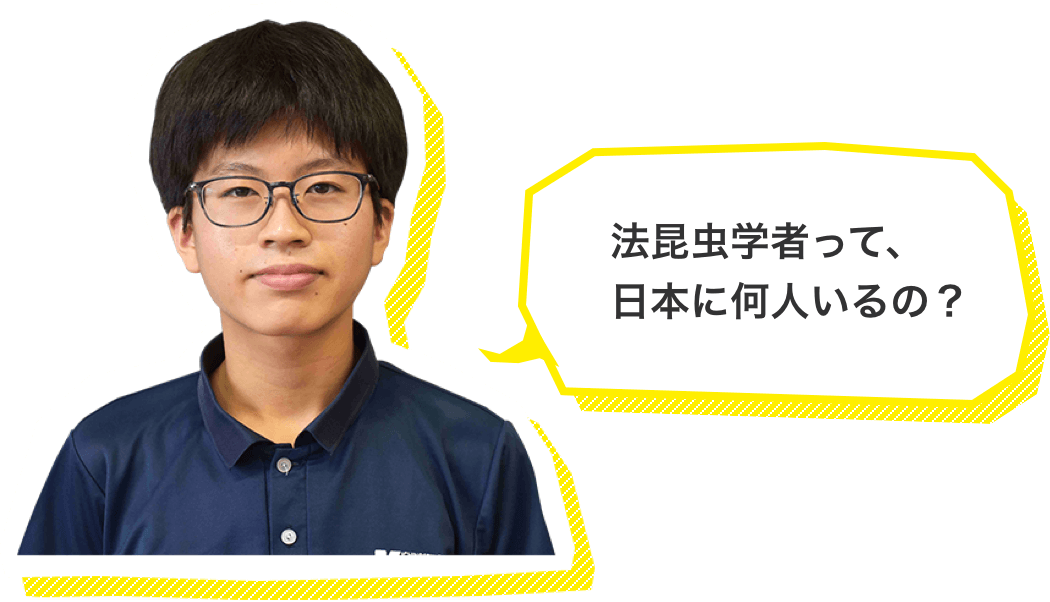
鈴木飛翔(すずき・あすか)さん(高校2年生)
- 三枝
- 研究を継続的にやっている人があまりたくさんいないのですが、お医者さんや科捜研の人の中に必要に迫られて昆虫の仕事をする人が少しずつ増えてはいます。
- 編集
- ということは、国内ではこの分野での研究連携は少ないのでしょうか。
- 三枝
- やはり、その辺が特殊ですね。昆虫が好きな人はたくさんいて、研究者も大勢いるのですが、警察が持っている情報はあくまでも捜査情報なので、あまりあちこちに出したくない。なので、優秀な研究者がいても、そこに話を通すことをしたがりません。例えば、話を研究者に持ち込んだとき、「これはあの人が専門だから」と他の人に振られると、情報が拡散してしまう。警察はそれが怖いというか、限られた人にしか情報を出したくないことがあります。
それから、昆虫の研究者も「これは死体から取ったものだ」と言うと、「うわっ」となる。死体に対する畏怖があり、「昆虫は好きだけど、死体は好きじゃない」と尻込みしてしまうので、ネットワーク化しにくいところはありますね。
- 鈴木
- 先生、頑張ってください。
- 三枝
- ありがとうございます。
●法昆虫学事始め
- 編集
- 2000年、バードとキャストナーの編著 “Forensic Entomology: The Utility of Arthropods in Legal Investigations”(法昆虫学:法的捜査における節足動物の有用性)という本を青木教授から渡され法昆虫学を始めたとのことですが、このテーマをどう展開されていったのでしょう。
- 三枝
- まず「どういう状態の死体に、どんな種類の昆虫が入るか」を調べようと思いました。当時、昆虫が付いている法医解剖の例も多くなかったので、法医学教室で持っていた設備を使い、ウジを飼って成虫まで孵(かえ)していました。
学生時代、私は野ネズミなどの染色体の研究をしていたのですが、同じ研究室に昆虫の染色体を研究している同級生がいました。彼は昆虫採集が趣味で、昆虫標本の作り方を熟知していました。その同級生にくっついてというか、脇で見ていて、どういう道具が必要かなど見よう見まねで覚えていました。昆虫の種類の同定は専門的で難しいのですが、その友達が「オスの生殖器の形態で見分ける」と言っていたので、ハエの生殖器の形態の文献を探したり、まずはそういう形で入りました。
ただ、昆虫の同定は非常にマニアックな世界で、「この毛が3本か5本で見分けます」「そんなのわかんないよ」という感じ。で、どうしたらいいか迷ったあげく、当時はやっていたDNAの塩基配列で比較することをやってみました。形態的に同定するとともに、DNAを取って塩基配列を比較する。そのデータが蓄積されると、ハエを成虫にしなくてもDNAの塩基配列で種類がわかるようになります。
DNAの塩基配列を解析する機器は全国の科捜研や法医学教室にあるので、全国展開できるかなというのがきっかけです。その後、生物の世界ではDNAバーコーディング※が注目され、その走りというか、その部分をやっていたという感じでしょうか。
※DNAバーコーディング:短い遺伝子マーカーを利用してDNAの配列から種を特定する系統学的手法。
●忘れられない思い出
- 編集
- これまでの研究で忘れられないエピソードといえば?
- 三枝
- どうでしょう。やはり本にも書いた韓国の朴成桓(パクソンファン)先生とやり取りでしょうか。
- 編集
- あのセウォル号の?
- 三枝
- ええ、そうです。彼は日本語が堪能で、ほぼ日本語でやり取りしたのですが、韓国ではこのケースが法昆虫学鑑定の初事例となりました。私はメールを2~3回差し上げただけなのですが、2017年、高麗大学校医科大学で行われた「死後経過時間推定に関する国際シンポジウム」に講演者として招待していただいたとき、会場で「ああ、あなたが!」と言われたので、逆にびっくりしました。
- 編集
- 海外との連携になりますね。
- 三枝
- そうですね。
- 編集
- ありがとうございます。
コラム
朴成桓教授による韓国初の公式な法昆虫学鑑定
2014年4月、韓国南西の海域で大型旅客船セウォル号の転覆・沈没事故が発生。この旅客船の運営会社の会長は逃亡したが、約2カ月後、身元不明の腐乱死体で発見された。身元はDNA型鑑定によって判明。高麗大学校医科大学法医学教室の朴成桓教授は、死体に付着していたウジから男性の死後経過時間を推定し、これが韓国初の公式な法昆虫学鑑定となった。