中高校生が第一線の研究者を訪問
「これから研究の話をしよう」
第23回
小さいけれど広い世界。
原生生物の動きを探る
終章 みんなの感想
知れば知るほど面白い原生生物
岡山ひかりさん(中学1年)

西上准教授の講義では、普段の学校生活では得られない貴重なお話を聞くことができました。ミズヒラタムシには足があること、ロクロクビムシは体が残っていれば頭を切っても大丈夫な話や、星の砂はタイヨウノスナなどの死体だという面白いことまで教えてもらいました。粘菌の研究室にも入れ、たくさんの機器があることに驚きました。特に驚いたのは、3Dプリンターで部品を作って小さいものを見られるようにしていたことです。今までは目に見えないものだからあまり興味が湧かなかったけれど、今回で興味を持てたので疑問に思ったことはすぐに調べて学びを深めたいです。
昆虫以外にも興味深い生き物がいる!
神野由徠さん(中学1年)

自分は昆虫以外、原生生物にはほぼ興味がなかったのですが、北大で粘菌の話を聞いて菌類を含め原生生物も面白いのだと感じました。具体的には、粘菌も好んで食べる物があることや、湿度や食料の量などによって起こる状態がクマムシのクリプトビヨシス※に似ていたり、人間と菌類が思っていた以上に近かったことです。そして、たとえ生物の研究だとしても、研究には数学など生物以外の知識も大切だと聞いて、今後は自分の好きな教科だけではなく、さまざまな教科をまんべんなく勉強していこうと思いました。
※クリプトビオシス(cryptobiosis:隠された生命活動):特定の生物が乾燥や極低温などの厳しい環境に対して生命活動を停止する無代謝状態のこと。
幅広い勉強が必要だと分かった1日
佐々木健翔さん(中学1年)
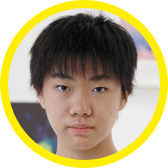
今回、北大で原生生物の話を聞き、特に印象に残ったことについて感想を書きたいと思います。まず粘菌の話は、原生生物で単細胞なのに迷路を最短距離でゴールまで行くという、絶対に考えないとできないことをやっていて、「もう僕より頭いいじゃん」と思いました。次は線虫。僕も線虫は顕微鏡などで結構見てきたのですが、まさかジャンプするなんて思いませんでした。3つ目が勉強の話です。先生から「何を研究するにしても、いろいろな教科を使う」という話をお聞きしました。これは、これからの勉強についてめちゃくちゃ考えないといけないなと思いました。やはり論文を読むのには英語力が必要ですよね。僕は英語が苦手なのですが、先生の話を聞いて頑張ろうと思いました。今回は貴重なお話をありがとうございました。
※線虫のジャンプについてはこちらを参照
自分の目で見た原生生物が新鮮
泉一生さん(高校1年)

西上先生の講義を受けて、原生生物という普段目で見ることができず、気にもかけていなかったとても小さな生物について知ることができました。これまでの微生物についての学習は実際の姿を見ず、ただ写真を見て暗記することばかりでしたが、自分で顕微鏡を作って原生生物の姿を見ることで、アメーバの動きの少なさやミドリムシの活発性など、写真では分からない情報を自分の目で確認することができました。また、西上先生が生物の研究をしている中で物理や数学が必要であったように、自分も選択した科目だけにとらわれず、視野を広く持って研究に取り組むべきであることを学びました。
ミクロの世界の楽しさを実感
大山莉璃羽さん(高校1年)

原生生物については、気にしたこともなく、何も分からない状態でした。でも今回、原生生物についての講義を聞いて、人間が肉眼で見ることの難しい世界にこんなに楽しい世界が広がっているのだとワクワクしました。あんな小さな世界でも、食べる・食べられるの関係があるのもすごいなと思いました。今まで気にしなかった世界に目を向けたら、これから生活していく時もいろいろなところが気になって楽しくなりそうです。ありがとうございました。
目に見えない世界に近づけた
正村悠結さん(高校1年)

原生生物についてまったく知らず興味もなかったのですが、小さい世界があんなにも大きく広がっていることを知ることができました。事前に読んだ本ではあまり実感が湧かなかったけれど、先生の講義を聞いたり、実際に動いているところを見たりして彼らに近づくことができてよかったです。最後に「生物なのに結局は物理や数学が必要になった」とおっしゃっていたのが印象に残っていて、実際、どんな知識がどこで必要になるのか分からないから、もっとたくさんのことをえり好みせず勉強したいなと思いました。
原生生物の多様性にワクワク
淀野佑也さん(高校1年)

原生生物については、中学生の時にその構造をほんの少し習った程度でした。原生生物はせいぜい動物性か植物性かくらいに思っていましたが、事前に読んだ本や西上先生のお話を聞いて、その多様な進化に驚き、とてもワクワクしました。先生の話す様子は本当に楽しそうで、1つのことに熱中できることを尊敬したし、私も自分の興味のあることを深掘りし、熱意を持って取り組んでいけたらと思いました。今回の訪問、本当にありがとうございました。
楽しい経験が学びのモチベーションに
教諭:青野裕幸(あおの・ひろゆき)先生

原生生物という構造的には極単純だと思っていたものたちが、実に複雑で論理的な動きをしていることに驚かされました。今回参加した生徒たちが興奮モードになっていたのも理解できます。学習に対してどのようなモチベーションが必要なのかということも実体験を元に教えていただけたので、学校に戻った今回の参加者が良きインタープリターとして活躍してくれたらと思います。もっと多くの生徒たちに、このような最前線の研究に触れる機会を設けることができればと、心底思わされる機会でした。今回の訪問を契機に、身の回りのさまざまなことにもっと目を向けるきっかけをうまく作っていきたいと思いました。本当にお世話になりました。