中高校生が第一線の研究者を訪問
「これから研究の話をしよう」
第14回
キリンの首がよく動くのはなぜ?
生き物の身体の形と機能に潜む“意味”を探究
第2章 教えて、郡司先生!
●研究についての不安
- 坂入
- キリンに関する研究がまだ少なかった頃、研究を始められたそうですが、不安はなかったのですか。
- 郡司
- 最近の学生さんは不安を気にする方がとても多いのですが、不安は何をしていても解消されることはありません。研究をしている以上、誰もやっていないことのほうが未来が開けています。というのも、研究は誰も知らないことを突き詰めていく作業なので、みんながやっていたり、わかっていることがたくさんあるほうが、研究をしていく上では大変な面もあるからです。もちろん、先生が少ない、直接教えてくれる人がいないという不安はありますが、教えてくれる人がたくさんいるということは、それだけライバルも多いということ。私の場合、誰かと競うより、自分のペースで研究を進めるほうが性格上、向いているなと感じていました。

坂入碧衣さん(高校2年)
●チャンスを生かすために
- 前田
- 先生は『キリン解剖記』の中で、提供されたオカピやキリンの赤ちゃんを「ここぞ」というときまで冷凍庫で保管していたと書かれていました。逆に、献体してもらった動物を「ここぞ」ではないときに解剖してしまったこともあるのですか。
- 郡司
- それはたくさんあって、「勉強不足だったな」と解剖の最中に気づくこともありました。赤ちゃんなら冷凍庫で保管できますが、例えば大人のゾウだと入らないので、亡くなったタイミングですぐ解剖しなくてはなりません。「もっと勉強しておけばよかった」「あ、これはいまじゃない」と思いながら取り組むことも、やはりすごくたくさんあります。なので、いつ何があってもいいよう、チャンスが来たらきちんとつかめるよう、興味を広く持つなど日々準備をしておくことが大事です。
とはいっても、チャンスは本当に突然やってくるので、うまくキャッチできないときもあります。そういうときは、「次までにもう少しここを勉強しよう」と自分の中で学びとしていけば、それは1つのいい経験としてプラスになっていくのではないかと思っています。
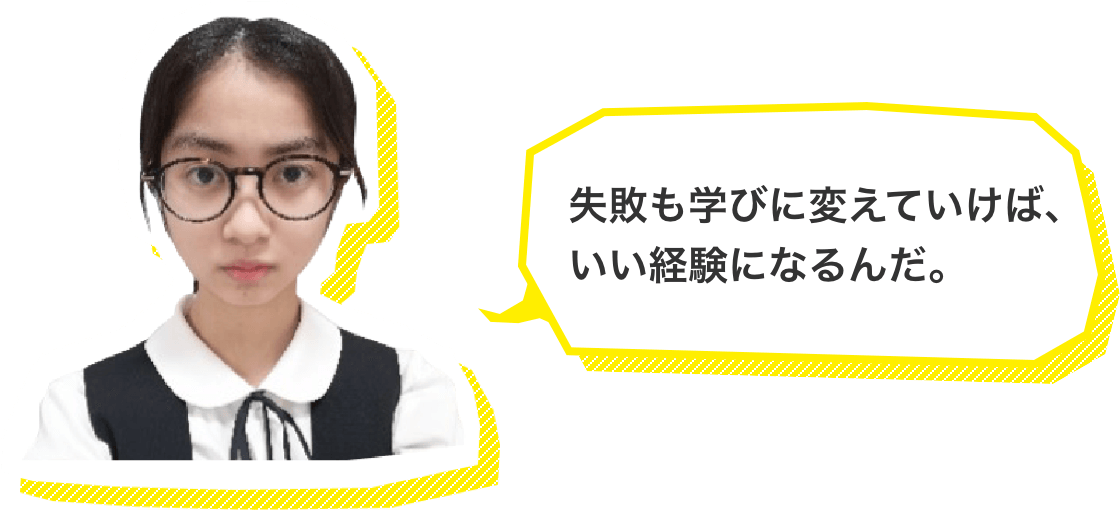
前田紗楽さん(高校2年)
●研究で大変なこと、楽しいこと
- 山田
- 先生が研究をしていく中で一番大変だったことは何ですか。
- 郡司
- 「大変だったこと、苦労したことは?」という質問をよく受けますが、実はあまり答えないようにしています。なぜかというと、大変だったことはすごく共感しやすいからです。例えば、ハードスケジュールや人間関係の悩みなど、どんな仕事でも大変な部分はわかりやすいんですね。
一方、研究で楽しかったこと、よかったことは共感しづらい。世界に自分しか知らないことの喜びは、想像はできても、なかなか実感できないのではないでしょうか。いいことと悪いことの想像のしやすさに大きなギャップあるのが、研究という活動です。なので、「これから研究者になってみたい」という若い皆さんには、想像しやすい大変なことのイメージに流されてほしくないと思っています。
でもね、大変なことも楽しいですよ。難しいなと思うことや壁にぶつかることがあっても、それは他の人にはなかなか経験できないことなので、振り返るとすごくいい経験というか、楽しいと思える経験になると思います。ちょっと意地悪な回答になってしまったかもしれませんが、そんな感じです。
●解剖での大変な作業
- 柏崎
- 解剖で一番大変な作業は、どういったことですか。
- 郡司
- 言葉通りの大変さでいえば、遺体を運んできて下ろすまでの作業。私自身、何十キロもある重いものを軽々と持てるほどのフィジカルは持っていないので、脚1本で80~100kgもある重いキリンをトラックから下ろし、解剖室まで運んでいくところは肉体的にハードですね。

●教諭からの質問
- 本多
教諭 - 教員が質問してもいいですか。
- 郡司
- もちろん、ぜひどうぞ。
- 本多
教諭 - 本の中に、首を切断する位置が違っていたことに気づいたという部分がありました。これは、どうやってひらめいたのでしょう。
- 郡司
- ひらめきなんていうカッコいい話ではありません。「何だかうまくいかない」「よくわからない」ということが続いたら、「ちょっと視点を変えてみよう」というのは、どんな仕事をしている人でも同じだと思うんですね。私の場合も、視点を変えていろいろな取り組みをした中に、先につながるような見方がたまたまあったという感じです。
- 山口
教諭 - 先生は大学4年生のときカイツブリの首振りの研究をされました。キリンの首もそうですが、そもそも首に興味があるのですか。
- 郡司
- 首というか、背骨が好きなんです。脊椎動物の最大の特徴は脊椎であり、脊椎は脊椎動物を知る上で不可欠だと感じています。また、頭や手足に比べ脊椎の研究は少ないので、首に限らず、生き物の背骨の多様性や機能を詳しく知りたいという気持ちが強くあります。
- 山口
教諭 - 生き物は多種多様で感心することがたくさんあるのですが、ここ最近で「これは面白い」と思った生き物の形や構造はありますか。
- 郡司
- 私自身、それなりに生き物好きだと思っていますが、それでも知らないことが圧倒的に多く、ちょっと解剖したり、観察するだけですぐに好きになってしまいます。最近、研究室の学生さんとレッサーパンダの研究をしています。レッサーパンダはあざとめのかわいさがあり人気ですが、とても器用に木に登り移動します。行動や身体の構造を観察していると、他のネコの仲間とは少し異なる特徴が見えて、改めてすごいなと感じます。なので、直近ではレッサーパンダかな。いろいろな動物を解剖すると「ああ、すごい。自分は何て無知なんだろう」と思うというか、動物の素晴らしさを感じることが多いですね。
- 山口
教諭 - あと、もう1つ。動画でキリンが自分のお尻をなめていたのですが、あれはよく見られる行動ですか。また、どうしてなめるのでしょう?
- 郡司
- しばしば見られる行動です。便は自身の健康のバロメーターでもあるので、気にする生き物は多いと思います。あと、尿にはフェロモンがたくさん含まれていて、例えば発情しているかどうかのキーとなるので、自分の尿や一緒に飼育されている他のキリンの尿を気にする個体は結構多いですね。
- 編集
- 編集からも1つ。ロボット開発を工学部の先生方と共同研究されているとのことでした。最近、コラボして研究する事例が増えているようですが、先生のきっかけは?
- 郡司
- SNSのTwitterです。私のTwitterを見た東大工学部の先生から「一緒に研究する人を探しているのですが、どうですか」というお話をいただき、何度かお会いした後、「ぜひ一緒にやりましょう」となりました。SNSが全盛なので、こういった始まり方は結構たくさんあり、50、60代の教授同士がSNSで出会い、共同研究を始めたというケースも耳にします。