中高校生が第一線の研究者を訪問
「これから研究の話をしよう」
第25回
「しっぽ学」の水先案内人に聞く
しっぽの不思議
第6章 最後のQ&A
集中講義、ニワトリ胚の観察、そして移動した研究室ではホルマリン漬けの標本やさまざまな実験機器を見学しました。再び実験室に戻り、東島先生に最後の質問です。
- 齋藤
- 先生は学部時代は文系で、修士課程から理系になられました。文系から理系になるのはすごく大変なことだと思うのですが、文系をやっていたからこそ、こんなことができたというようなことはありますか。例えば、ものすごく難しい『日本書紀』が読めたのも、漢文など文系の勉強をしたからなのでしょうか。
- 東島
- いいえ、『日本書紀』が読めることと、私が文学部出身であることは、全然関係ありません(笑)。文学部時代に『日本書紀』講読の授業はありましたが、私は受けていませんでした。ですから、『日本書紀』の読み方が全然分からなくて、2021年に京大に着任した後に一から勉強しました。何をやるにしても、遅すぎるということはあまりないと思いますよ。もちろん、文系から理系に行ったり、理系の中でも人類学から発生学に移るのは苦労が多く、なかなか難しいのですが、知りたいことがあるときは苦労も楽しいなと思えます。研究に限らず、視野を広く持つこと、いろいろなことを知っているほうが日々楽しいです。
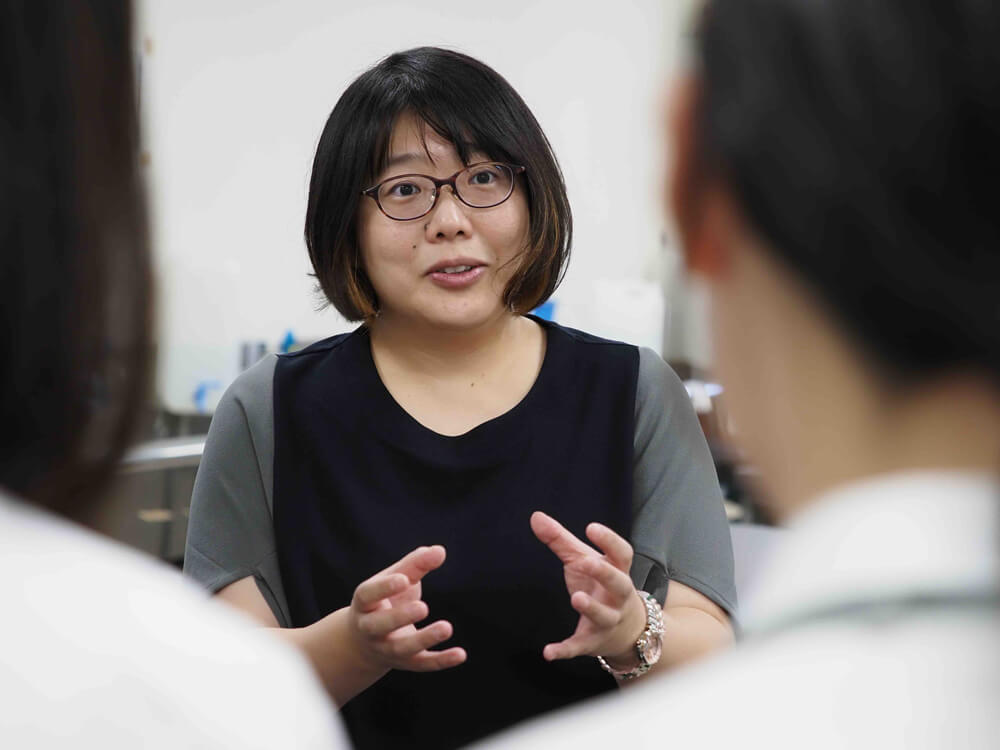
- 鈴木
- 今までやっていたのと違うフィールドに行くとき、新しい勉強は誰かから教わるのですか、それとも独学ですか?
- 東島
- 基本、自分でやります。それと、授業を受けるのは効率のいい勉強方法だと思います。大事なポイントが絞られているので、分かりやすいんですよね。大学に行ったらいろいろな学部の授業を受けられるので、興味のある学部の授業を受けにいくのはいい方法だと思います。あとは本を読んだり、論文を読んだりするのがいいかな。例えば、新書は基本的に大学生くらいを読者に想定して書いているので、皆さんが何か知りたいときの入り口にはちょうどいいかもしれません。
- 布目
- 自分の将来に迷いがあり、研究者がどういうものなのか知りたいです。研究者に必要な素質というか、どういう人が向いているのでしょう。
- 東島
- 難しいですね。いろいろな人がいるので、一概にこうとは言えないのですが、やはり今もっている「動物が好き、生物が好き」という気持ちはずっと大事にしてほしいと思います。好きだったら、よく見ると思うんですよ。生き物の研究の基本は見ることだと思います。どれだけ長く、どれだけ詳しく、その生き物のことを見られるか。
ちょっとしたオタク気質と生物が好きという気持ち、あとはフットワークを軽くすること。「暑いから行くのは面倒だ」「しんどいからやめておこう」と、やらない理由や行かない理由はいくらでも見つけられますが、「ちょっと行っておくか」とフットワークを軽くすると、いろいろな情報が入ってくるし、人とも知り合える。そういうフットワークの軽さは大事ですね。

- 浅見
教諭 - 最後に、今日は女性ばかりなのでお聞きしたいのですが、女性であることでデメリットを感じたことがありますか。
- 東島
- 私はあまり参考にならないかもしれません。というのも、正直、私自身は研究者をやっていて男女を意識したことは全くないからです。女性限定公募とか、女性を増やしなさいというお達しが文部科学省から全国の大学に行っているので、女性研究者や女子学生、特に理系を採ろうという動きは社会的にたくさんあります。でも、そういう時勢だからこそ、女性が採用された際に「あの人は女性だから採用された」と言う人だって出てくるわけです。もし自分がそんなことを言われたら、もちろん悔しいでしょうし、「それは違うだろう」とも思うじゃないですか。だから、例えばそういうことを言われたとき、自分の中に「いや、そうじゃない」と言える確固たるものがあれば、そんな讒言(ざんげん)は全然問題ではないと私は思います。