SCIENCE TOPICS いま注目の最先端研究・技術探検!
第14回 蛍光タンパク質を使って生きた細胞の活動をリアルタイムに観察~理化学研究所 脳科学総合研究センター・宮脇敦史先生を訪ねて
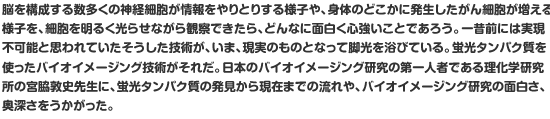
いま生命科学分野の研究で大きな貢献を果たしているのが蛍光タンパク質だ。当「生命科学DOKIDOKI研究室」でも、蛍光タンパク質を使ったさまざまな研究の成果を紹介してきた。からだの細胞が入れ替わる様子を観察した研究、ショウジョウバエのサナギの殻のなかで頭や胸・腹が踊るように動いて分かれていく様子を観察した研究、血液が流れだす瞬間をとらえた研究など、蛍光タンパク質はねらった細胞を光らせてその振る舞いを追跡する研究に活躍してきた。
蛍光タンパク質の研究に先鞭をつけたのが下村脩博士である。博士は、1960年代の初頭に、米国ワシントン州フライデーハーバーの海面に明滅するオワンクラゲから、カルシウム感受性発光タンパク質(博士がイクオリンと命名)と、緑色蛍光タンパク質(GFP=Green Fluorescent Protein)を精製し、オワンクラゲが緑色に光るしくみを解き明かしたのだ。

▲ 下村脩博士

▲ オワンクラゲ
ところで、光るのはオワンクラゲだけではない。ホタルや、ホタルイカ、夜光虫、チョウチンアンコウ、ツキヨダケ、ある種の熱帯魚やサンゴなど、800種類以上の光る生物が報告されてきている。面白いことに、それぞれの生物によって光るしくみは違う。ホタルは、からだの中にあるルシフェリンという発光物質にルシフェラーゼという酵素を働かせ光を作り出す。チョウチンアンコウは、発光バクテリアという光る細菌を体内に飼って光る。また、サンゴやイソギンチャクのいくつかは蛍光タンパク質を持ち、太陽光の中の紫や青の光を吸収して緑や赤の光を発する。
オワンクラゲの発光と格闘した下村博士の奮戦ぶりを宮脇先生が教えてくれた。 「オワンクラゲは、刺激を受けるとお椀のような傘のふちが緑色に光ります。博士は何十万匹ものオワンクラゲを採集し、傘のふちにある発光器を切り取るという気の遠くなるような作業の末、ようやく発光タンパク質の精製に成功しました。それがイクオリンでした。イクオリンは、タンパク質部分であるアポイクオリンと酸素分子、そして発光基質であるセレンテラジンからできています。アポイクオリン部分にカルシウムイオンが結合すると、セレンテラジンの酸化反応を経て青色の発光が起こることを博士はつきとめたのです」
しかし謎が残った。試験管の中でイクオリンが出す光は青色であって、一方、海の中でオワンクラゲが出す光は緑色である。なぜ、色が違うのだろうか。下村博士はさらに研究を続けた。
「下村博士は、イクオリンの傍らにあって緑色の蛍光を発するタンパク質を発見しており、これを精製することにも成功しました。これが、後にGFPと名づけられたタンパク質でした。GFP は、イクオリンの青色の光を放つべきエネルギーを奪って、代わりに緑色の光を放っていたのです」
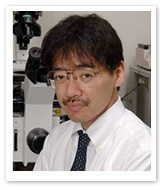
1961年岐阜県生まれ。1987年、慶應義塾大学医学部卒業、91年大阪大学医学部大学院医学研究科博士課程修了(生物神経生物学)、東京大学医科学研究所助手、95年カリフォルニア大学サンディエゴ校ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム博士研究員を経て、99年より理研BSIに。現在、先端技術開発グループグループディレクター兼細胞機能探索技術開発チーム シニア・チームリーダー、理研BSI-オリンパス連携センターセンター長、科学技術振興機構(ERATO)研究総括。早稲田大学理工学術院 客員教授。主著に『蛍光イメージング革命―生命の可視化技術を知る・操る・創る』ほか論文多数。

