ARCHIVE 開催レポート
サイエンスカフェ2025
1道15県から32名の高校生が参加
2025年7月25日(金)・26日(土)

■スケジュール
1日目 7月25日(金)●ホテルグランドヒル市ヶ谷
-
①
「人体化する新治療機器」
早稲田大学理工学術院 創造理工学部 総合機械工学科 教授/医療レギュラトリーサイエンス研究所 所長 岩﨑清隆先生 -
②
「心臓をつくる―再生医療最前線」
東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 所長・教授 清水達也先生
2日目 7月26日(土)●TWIns
■参加校
市立札幌旭丘高等学校
秋田県立横手高等学校
岩手県立一関第一高等学校
宮城県仙台第一高等学校
福島県立会津学鳳高等学校
新潟県立柏崎高等学校
石川県立小松高等学校
福井県立高志高等学校
静岡北高等学校
長野県諏訪清陵高等学校
三重県立松阪高等学校
兵庫県立加古川東高等学校
島根県立益田高等学校
山口県立徳山高等学校
徳島県立富岡西高等学校
鹿児島県立甲南高等学校
サイエンスカフェ2024
15県から32名の高校生が参加
2024年8月9日(金)・10日(土)

■スケジュール
1日目 8月9日(金)●ホテルグランドヒル市ヶ谷
-
①
「人体化する新治療機器」
早稲田大学理工学術院 創造理工学部 総合機械工学科 岩﨑清隆 教授 -
②
「心臓をつくる―再生医療最前線」
東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 所長 清水達也 教授
2日目 8月10日(土)●TWIns
■参加校
青森県立青森高等学校
栃木県立大田原高等学校
千葉県立佐倉高等学校
神奈川県立厚木高等学校
富山県立富山中部高等学校
愛知県立一宮高等学校
愛知県立時習館高等学校
和歌山県立海南高等学校
島根県立松江南高等学校
岡山県立津山高等学校
高松市立高松第一高等学校
愛媛県立松山南高等学校
佐賀県立致遠館高等学校
長崎県立長崎西高等学校
大分県立佐伯鶴城高等学校
熊本県立鹿本高等学校
サイエンスカフェ2023
12道県から30名の高校生が参加
2023年7月28日(金)・29日(土)

■スケジュール
1日目 7月28日(金)●ホテルグランドヒル市ヶ谷
-
1.
「未来の医療を創る:医工融合による革新」
東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 先端工学外科学 正宗賢 教授 -
2.
「幹細胞から心臓をつくる―再生医療最前線」
東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 所長 清水達也 教授
2日目 7月29日(土)●TWIns
■参加校
札幌日本大学高等学校
山形県立米沢興譲館高等学校
茨城県立竜ヶ崎第一高等学校
茨城県立並木中等教育学校
埼玉県立松山高等学校
山梨県立甲府南高等学校
北杜市立甲陵高等学校
群馬県立前橋女子高等学校
岐阜県立恵那高等学校
奈良学園中学校・高等学校
広島大学附属高等学校
高知県立高知小津高等学校
福岡県立城南高等学校
福岡県立鞍手高等学校
宮崎県立宮崎西高等学校
サイエンスカフェ2022
13道府県から26名の高校生が参加
2022年7月27日(水)オンライン開催

■スケジュール
再生医療の最前線~細胞シートを用いたティッシュエンジニアリング~
東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 所長 清水達也教授

-
1.
ティッシュエンジニアリング~医療から食料まで~
東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 代用臓器学分野 高橋宏信講師、
早稲田大学 先進理工学研究科 生命医科学専攻 博士課程2年 岡本裕太さん、
アメリカペンシルベニア大学3年生 筧路加さん
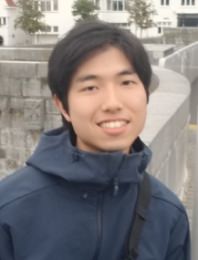
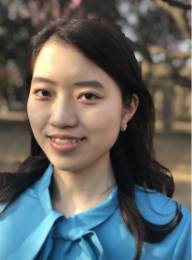

-
2.
最先端の手術室 「Smart Cyber Operating Theater: SCOT」
東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 先端工学外科学分野
吉光喜太郎特任講師、山口智子特任助教


-
3.
左右非対称性の進化生物学
早稲田大学教育・総合科学学術院 理学科生物学専修/
大学院先進理工学研究科生命理工学専攻
細将貴准教授、修士1年 秋元洋希さん、学部4年生 石川みのりさん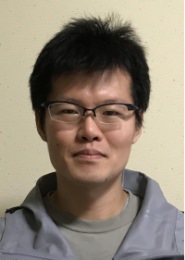
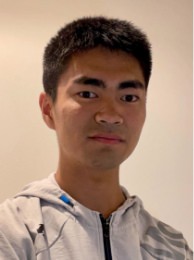

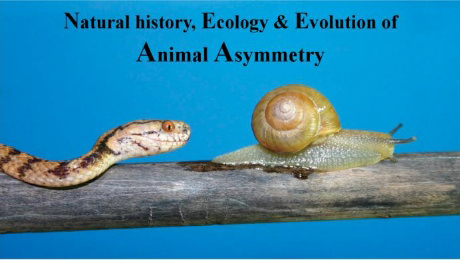
■参加校
北海道北見北斗高等学校
北海道釧路湖陵高等学校
山形県立酒田東高等学校
新潟県立新発田高等学校
福井県立武生高等学校
三重県立四日市高等学校
京都府立洛北高等学校
鳥取県立鳥取西高等学校
香川県立観音寺第一高等学校
徳島県立脇町高等学校
佐賀県立致遠館高等学校
長崎県立長崎南高等学校
大分県立大分舞鶴高等学校
沖縄県立球陽高等学校
